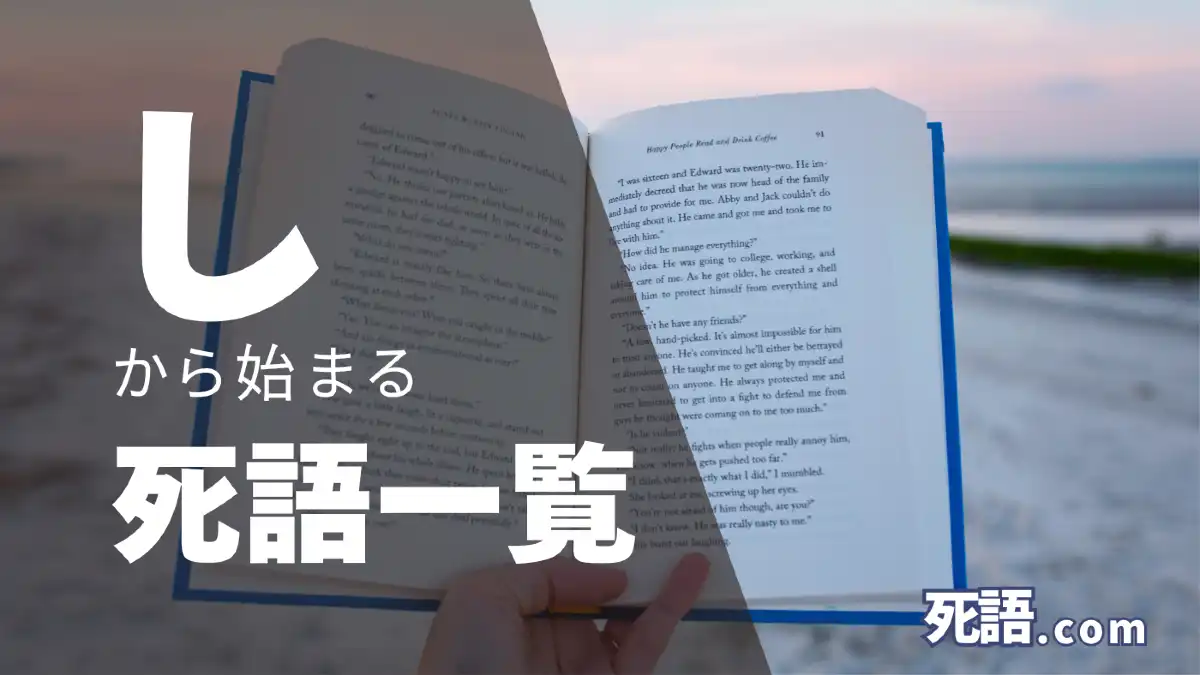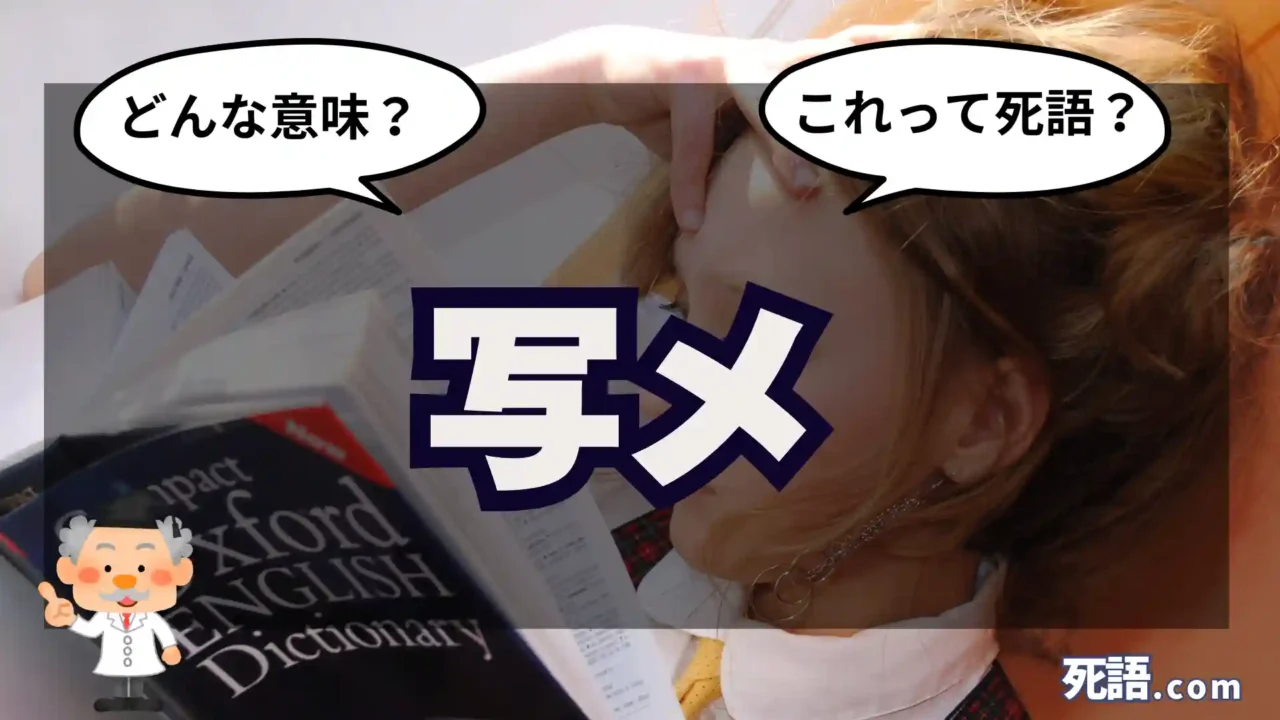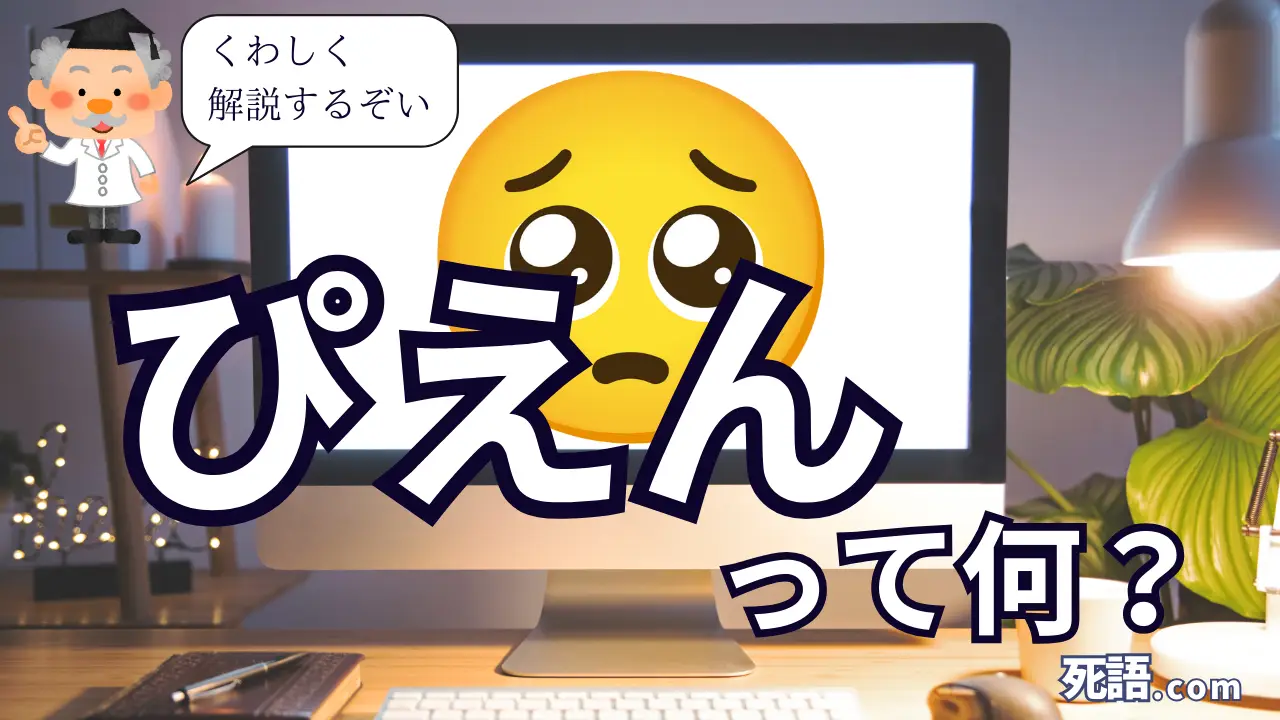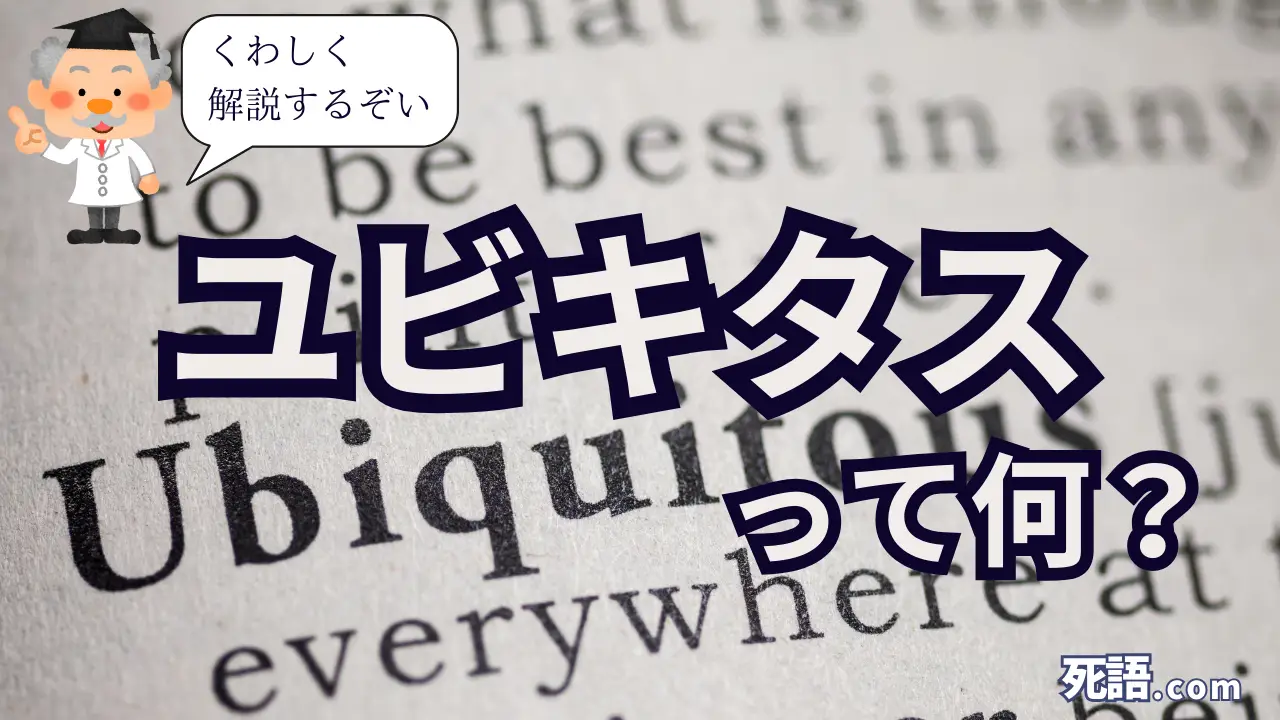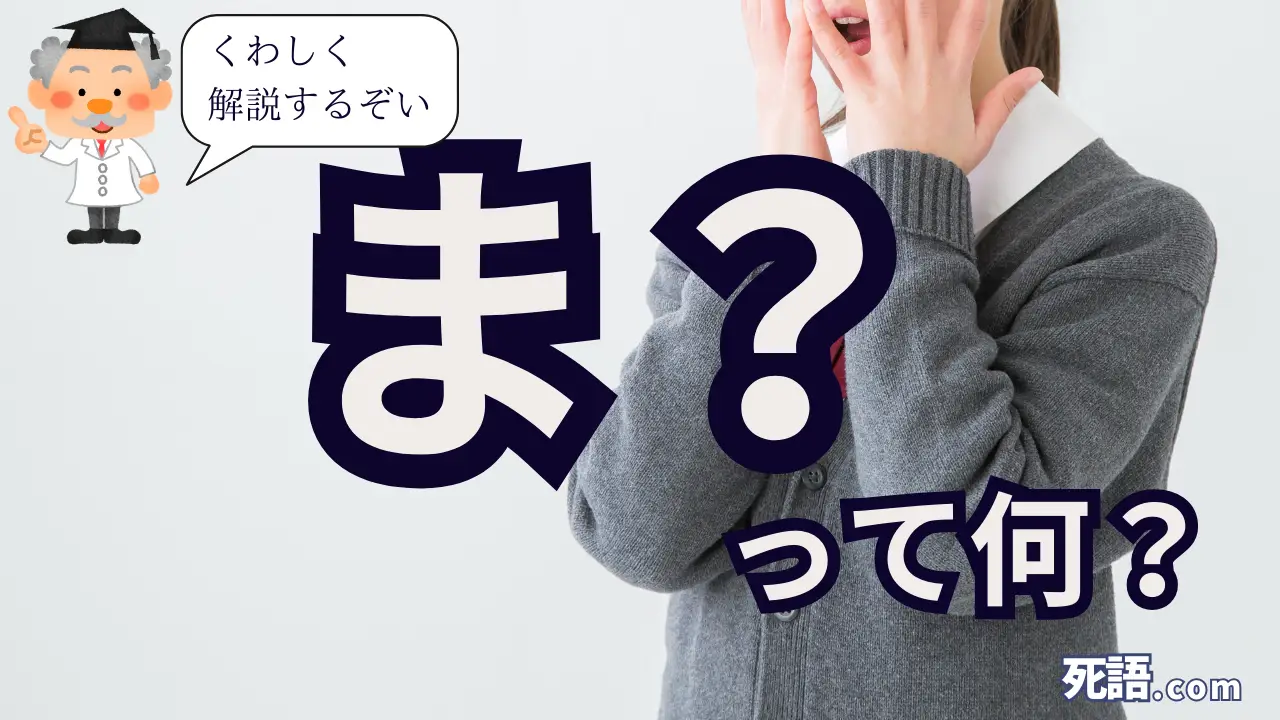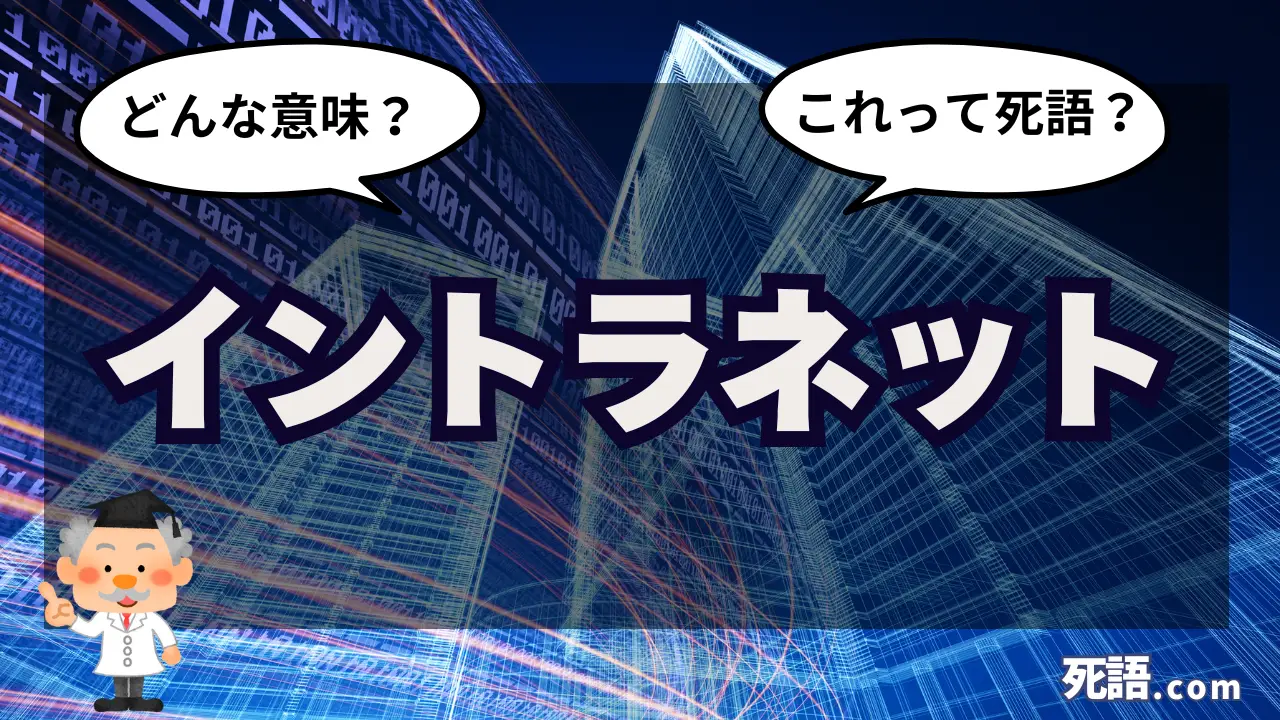記事では今は使われなくなった、「し」からはじまる死語を紹介します。
 博士
博士昭和からバブル経済期、平成から令和と、今では使われなくなった言葉のすべてが、わしの研究対象じゃ!
聞いたこともない古い言葉から、IT用語や流行語など、あらゆる死語を徹底的に集めました。
中にくすっと笑ってしまう死語や、問題ありな時代を感じるブラックな死語も。



普段なにげなく使ってる、その言葉も、すでに死語かもしれんぞい!
死語を知ることで、時代がわかる! 「し」から始まる死語をお楽しみください!
タップできる索引
本記事のリンクには広告が含まれています。
死語とは
死語とは、古くは一般的に使用されていたり、流行したが、現在では使われなくなった言葉です。
「しあ」~「しお」で始まる死語一覧
「しあ」~「しお」で始まる死語の一覧です。
地上げ
読み方
じあげ
意味
土地を買収して再開発するために、地主や住民に交渉し、時には強引な手法で立ち退きを迫る行為。
地権者が住民の合意無しに土地を売り払い、暴力団などが悪質な方法で住民を追い出すこともあった。
1980年代後半の、バブル経済で地価があがった時期にたびたび起きた。
バブルの崩壊により、多くの空き地や不良債権を生みだした。
GS
読み方
じーえす
意味
グループ・
サウンドの略。
和製英語。
エレクトリック・ギターなどの電気楽器を使った、数人で編成されがロックグループ。
ジャズ喫茶、ゴーゴー喫茶を中心に活動した。
1967年(昭和42年)から1969年(昭和44年)にかけて日本で大流行した。
ベンチャーズやビートルズ、ローリング・ストーンズなどのロック・グループの影響を受けていた。
G.F
読み方
じーえふ
意味
ガールフレンド(彼女)を意味する略語。
1950年代に流行した、元女生徒の隠語。
しーすー
読み方
しーすー
意味
寿司を意味する倒語で、1980年代の芸能・放送業界の業界用語。
シータク
読み方
しーたく
意味
タクシーの倒語で、芸能・放送業界の業界用語。
C調
読み方
しーちょう
意味
軽薄で調子がいいこと。
「調子」の音を逆さにした「しーちょう」から、「C調」になった。
芸能・放送業界の業界用語。
ジーパン
読み方
じーぱん
意味
「ジーンズパンツ」の略。
和製英語。
現代ではデニムパンツが一般的。
ジーンズの語源は、一説には「織物」の集荷地「ジェノバ製」からきている。
「ジェンズ (Genes)」、または「ジェノワーズ(Genois)」が、「ジーンズ(Jeans)」に変化したという。
シーマン
読み方
しーまん
意味
人面魚のこと。
ドリームキャストとPlayStation 2から発売されたゲーム、「シーマン」からきている。
音声認識でコミュニケーションできる育成ゲームだった。
週刊文春で「シーマンの顔がソフトバンクの孫正義に似ている」と報道すると、孫正義から開発者の斎藤あてに「仕込んだだろ!」と電話があったという。
シーマン CM お父さん編
- 出典:シーマン|ビバリウム(現:オープンブック)
シーマン CM お姉ちゃん編
- 出典:シーマン|ビバリウム(現:オープンブック)
シーマン CM PS2 お姉さん編
- 出典:シーマン|ビバリウム(現:オープンブック)
しーめ
読み方
しーめ
意味
ご飯(めし)を意味する倒語で、芸能・放送業界の業界用語。
特に外食をいう。
使い方



今日の夜、イタ飯屋にしーめ行こうよ
しーらんぺったんキュウリ
読み方
しーらんぺったんきゅうり
意味
「知らない」、または「どうなっても知らない」という意味。
使い方
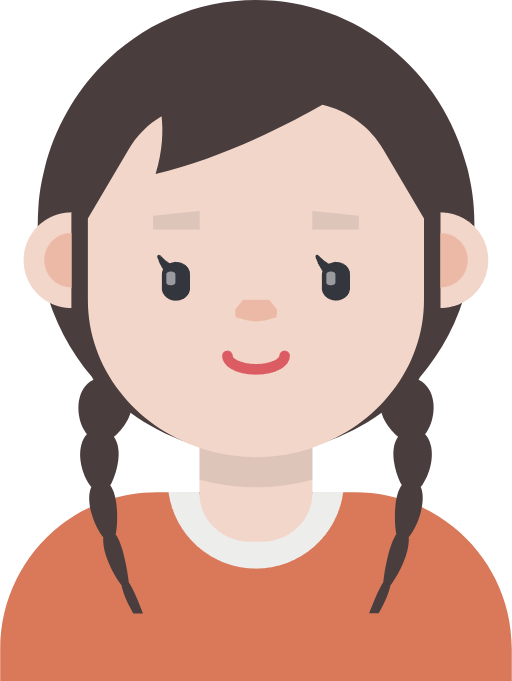
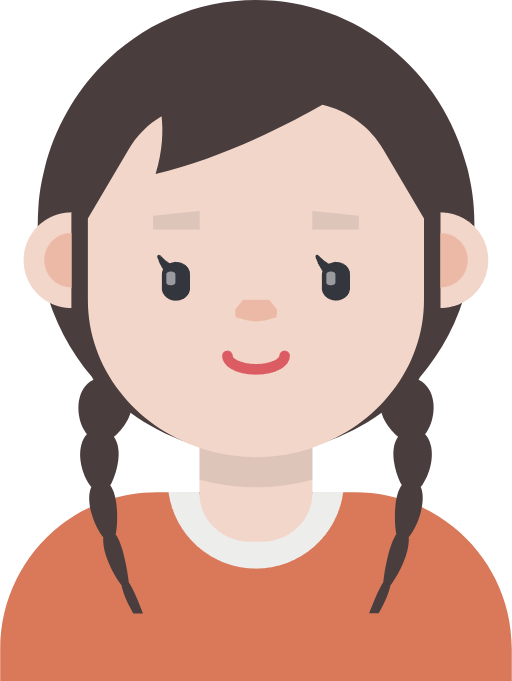
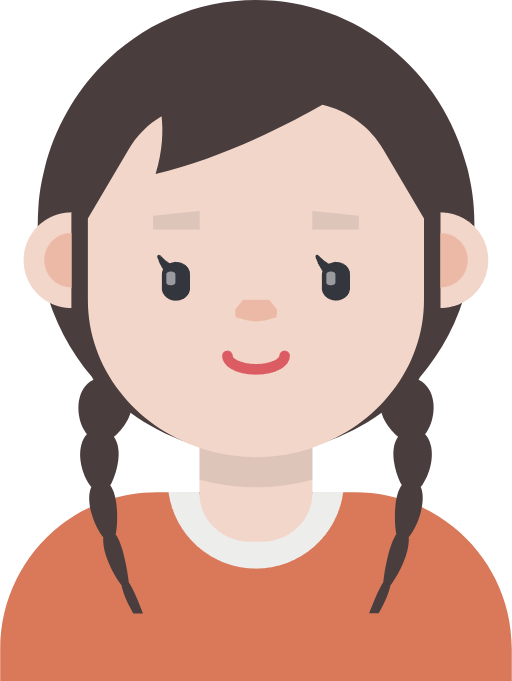
ああっ、お皿、割っちゃった!



しーらんぺったんキュウリ~
しーらんぺったん、ゴーリーラ
読み方
しーらんぺったん、ごーりーら
意味
「知らない」を意味する言葉遊び。
シーン
読み方
しーん
意味
静まり返った状態や場面を表す擬音語。
同意する人がいないなど、無反応や沈黙の状況を強調する際に使われる。
シェー


読み方
しぇー
意味
赤塚不二夫の漫画『おそ松くん』に登場するイヤミのギャグ。
「シェー」の掛け声とともに、独特のポーズをとる。
全国的に流行し、数々の有名人がメディアでこのポーズをとった。
由来は赤塚不二夫が新宿御苑で、当時の作画スタッフらに「人前で何か恥ずかしいことやって」と提案したことから。
のちの漫画家の高井研一郎が、アベックの前で「シェーッ」と叫んで逃げたのがヒントになった。
「シェー」という発音は、本来、「ヒェー」と叫ぶつもりが、イヤミの前歯がすき歯のため、空気が漏れて「シェー」となってしまったとされている。
ジェネギャ
読み方
じぇねぎゃ
意味
ジェネレーションギャップの略。
世代間の価値観や文化の違いを指す俗語。
シオシオのパー
読み方
しおしおのぱー
意味
元気がなく、しょげている様子を表す言葉。
がっかり。
由来は子供向けドラマ「快獣ブースカ」。
「しか」~「しこ」で始まる死語一覧
「しか」~「しこ」で始まる死語の一覧です。
しか勝たん
読み方
しかかたん
意味
「~が最高」を強調する若者言葉。
特定の分野で自分が最高と思うものや、何かを褒めるときに使う。
「推し活用語」として生まれた。
使い方



推ししか勝たん
シカベル
読み方
しかべる
意味
「ポケベル」の連絡を、「シカト(無視)」すること。
携帯電話が普及する前の、連絡手段がポケベルだった1990年代までの俗語。
敷布
読み方
しきふ
意味
布団カバー、またはシーツのこと。
しくよろ
読み方
しくよろ
意味
「よろしく」の倒語で、1980年代の芸能・放送業界の業界用語。
「4649」とも書く。
死刑!
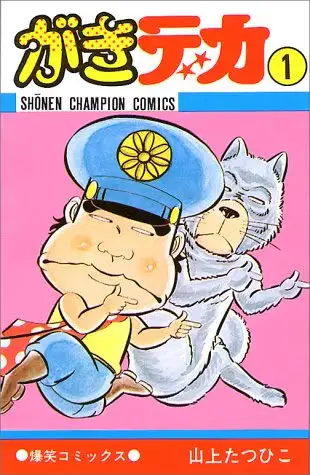
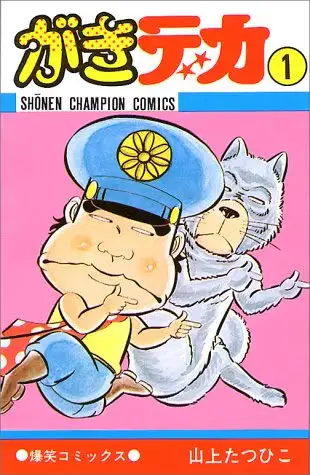
読み方
しけい
意味
山上たつひこによる日本の漫画『がきデカ』のギャグ。
両手の人差し指を突き出し、両手を組み合わせ、人のおしりに向けて発したフレーズ。
1974年から1980年『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)で連載されていた。
しけこむ
読み方
しけこむ
意味
遊郭や情事の場所などに入り込むこと。
江戸時代の遊女屋用語「時化込む」に由来する。
金欠状態を意味するスラングもある。
シケモク
読み方
しけもく
意味
吸殻からタバコ葉を回収して再巻きしたもの。
短い場合は竹串を刺して吸う。
戦後闇市時代の貧困層で流行した。
アニメ「ルパン三世」で次元大介がシケモクを吸う描写がある。
シケ単
読み方
しけたん
意味
試験にでる英単語の略。
昭和時代からの受験用英単語集のベストセラー。
関東では『デル単』、関西では『シケ単』と呼ばれる。
関連語
- でる単(昭和の人気の英単語集)
- 学参(学習参考書)
シケる
読み方
しける
意味
面白くないことや、盛り上がらないこと。
時化る。
戦後、ヤミ屋の言葉が一般に広まった。
昭和二十年代前半に流行語になった。
使い方
今日のライブ、シケてたね



お前こそ、そういうシタたこと、いうなよ
事件記者
読み方
じけんきしゃ
意味
事件を扱う新聞記者のこと。
昭和30年代に使われた。
しごおわ
読み方
しごおわ
意味
「仕事終わった」の略。
SNSなどで使われていた。
しごでき
読み方
しごでき
意味
「仕事ができる」の略語。
予想を超えた配慮、気遣い、サービス、パフォーマンスに対して使う。
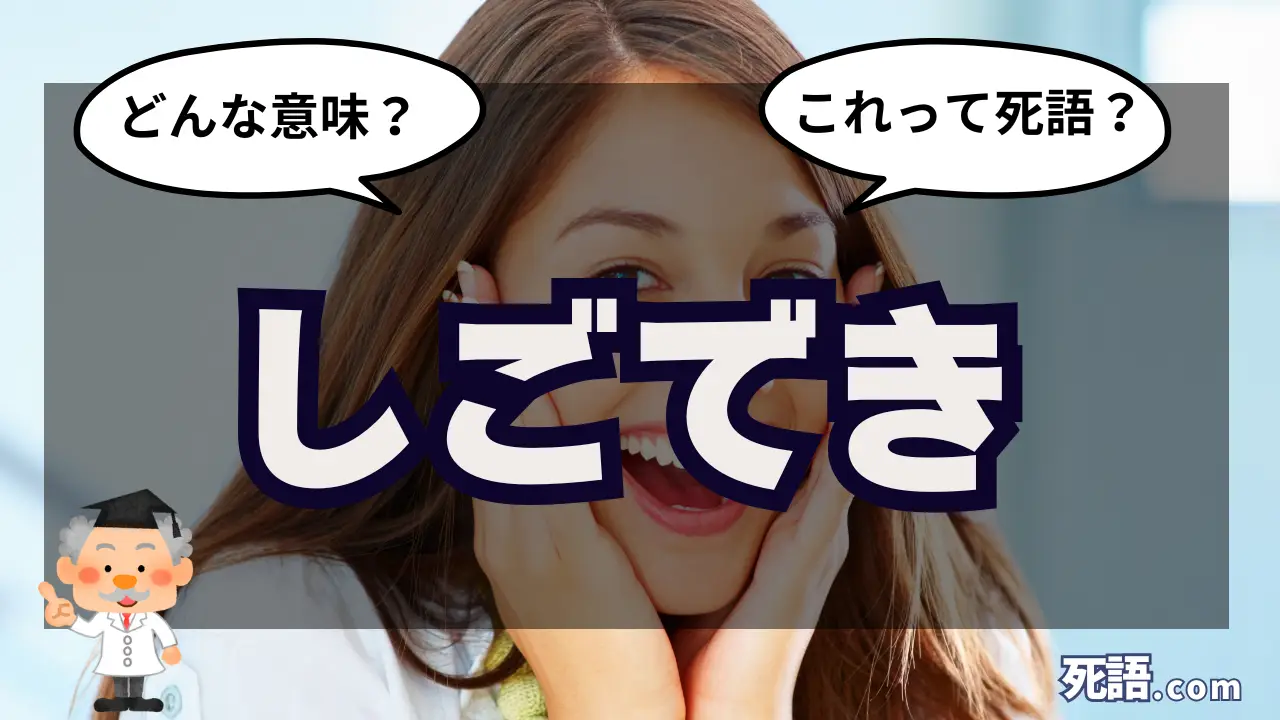
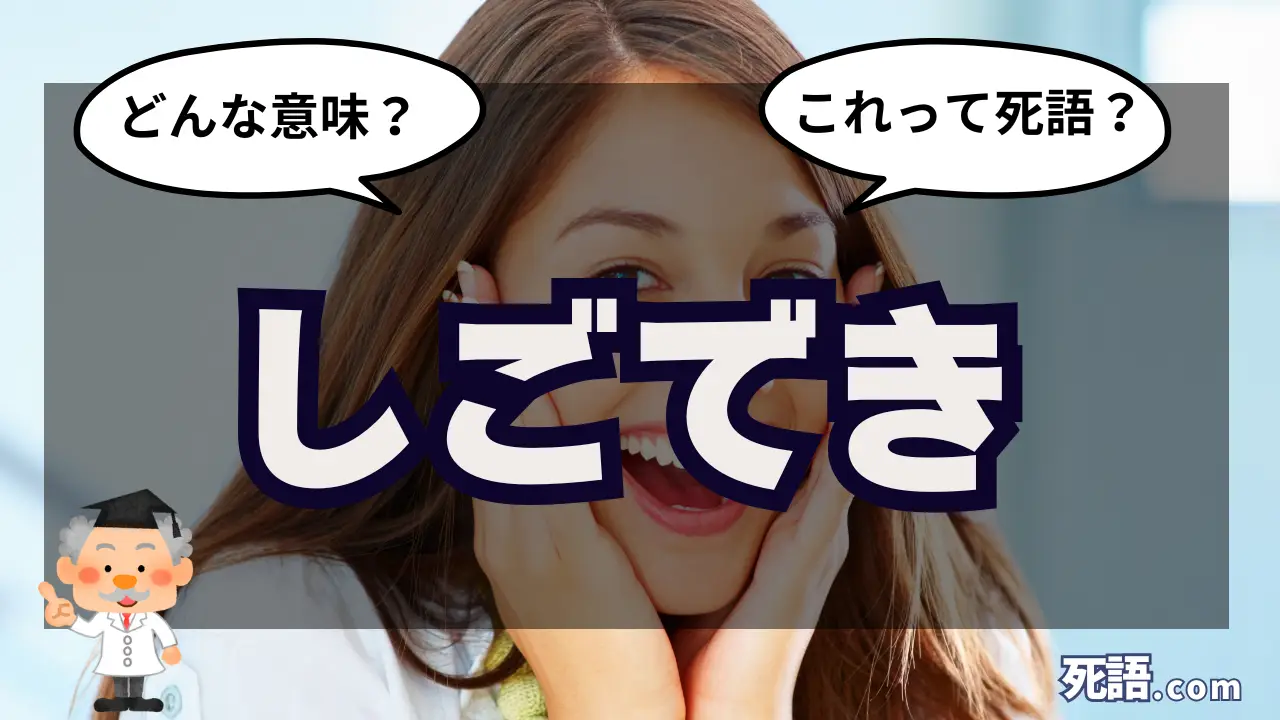
しこたま
読み方
しこたま
意味
数量がひじょうに多いこと。
特にお金について言う。
語源は上方語の「しこためる」からきているという説がある。
「しこ」は「頻(しき)る」の変化した「しこる」の語幹。
「ためる」は「貯める」。
江戸語から使われ始めた。
「どっさり貯める」から。
自己批判せよ
読み方
じこひはんせよ
意味
全共闘運動で用いられた思想統制用語。
学生運動が盛り上がった1960年代に流行した。
過激派内部での相互監視システムを言語化した表現。
使い方
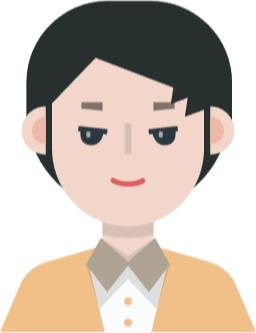
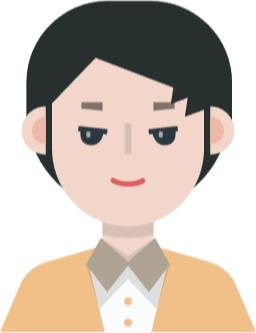
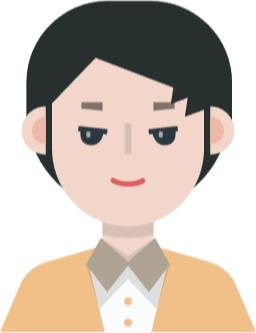
君、それは仲間を裏切ることと同じだよ、自己批判せよ
ジゴロ
読み方
じごろ
意味
女性に養われている男性。
「女たらし」の隠語、ひも。
1950年代に流行した「女たらし」の隠語。
語源はフランス語「gigolo」で、「年上の女性(と付き合い、その女性)から援助を受けている、あるいはどのように生活を成り立たせているのかはっきりしない、若い男」という意味。
「しさ」~「しそ」で始まる死語一覧
「しさ」~「しそ」で始まる死語の一覧です。
自殺点
読み方
じさつてん
意味
サッカーで味方ゴールに誤って得点すること。
1994年FIFAワールドカップでのコロンビア代表事件を契機に、日本サッカー協会が「オウンゴール」に改称した。
米国戦でオウンゴールを献上した、コロンビア代表DFのアンドレス・エスコバル選手が、母国で暴漢の凶弾に倒れ、命を落とした。
死して屍拾う者無し
読み方
ししてしかばねひろうものなし
意味
江戸時代の隠密同心の心得のこと。
隠密同心とは
江戸時代の徳川幕府の幕閣における役職名。
現代でいう秘密警察や特命刑事。
「隠密同心心得之條。我が命我が物と思わず、武門之儀あくまで陰にて、己の器量伏し、御下命如何にても果す可し。尚、死して屍拾う者なし。死して屍拾う者なし」
- 「我が命我が物と思わず」自分の命は自分のものではなく、庶民を守るためのものである。
- 「武門の議あくまで陰にて」武士としての能力や身分を隠し、表に出してはいけない。
- 「己の器量を伏し」自分の能力を隠し、表に出さない。
- 「御下命如何にても果す可し」どんな命令でも必ず遂行しなければならない
- 「尚、死して屍拾う者無し」任務中に死んでも、誰も遺体を拾って弔うことはない。
隠密同心が自分の存在を隠し、命をかえりみず、任務を遂行する覚悟を表している。
テレビドラマ「大江戸捜査網」で有名になった
地震・雷・火事・親父
読み方
じしん・かみなり・かじ・おやじ
意味
当時の世の中で、怖いとされる順番に並べたもの。
儒教的な家族観や、家父長制がまだ色濃かった昭和時代に、父親は恐れられていた。
ジスイッザッペーン
読み方
じすいっざっぺーん
意味
英語教育が浸透していなかった時代に、英語が話せるか問われたときに返す、ジョーク。
○○シスターズ
読み方
しすたーず
意味
TV番組で、人気アイドルや、声優を集めてユニット化したときに、○○シスターズと安易に名前をつけられることが多かった。
シスターボーイ
読み方
しすたーぼーい
意味
女性のような言葉遣いや、態度の若い独身男性のこと。
1957年公開の米国映画『お茶と同情』から流行した。
「秀麗な女装でありながら、男声で歌ってみせる歌手」や、「女性的な風貌の青少年」などがいた。
シスターボーイと恋愛するオバ様族を「お茶と同情族」と呼ぶようになった。
しずる
読み方
しずる
意味
ステーキがジュージュー焼けている様子を表現した言葉。
英語「sizzle」(ジュージュー音)が語源。
1980年代の広告業界で「シズル感」として、食品のみずみずしさを表現する専門用語になり、一般に俗語化した。
自然が私を呼んでいる
読み方
しぜんがわたしをよんでいる
意味
生理現象でトイレに行きたくなった時に使う。
1996年に日本でも流行したアメリカのテレビドラマ「フレンズ」でも、同様の表現があった。
「した」~「しと」で始まる死語一覧
「した」~「しと」で始まる死語の一覧です。
~しちった
読み方
しちった
意味
「~してしまった」の口語的表現。
北関東の方言が広まった。
実演
読み方
じつえん
意味
コンサート
北島さぶちゃんの実演があるので観に行こう
人前で実際に何かを行って見せることを指します。特に商品の機能や使い方を顧客に直接示す「実演販売」という表現が一般的です。披露と似た意味を持ちますが、実演の方がより具体的な行為を示す傾向があります。
失敬
読み方
しっけい
意味①
人に対して礼を失した振る舞いをすること、またはそのさま
意味②
先に席を立つこと、または人と別れること。
意味③
他人のものを黙って自分のものにすること、盗むこと。
類義語に「ぱくる」がある。
じっと我慢の子であった
読み方
じっとがまんのこであった
意味
1972年にレトルトカレーの元祖、大塚のボンカレーのTVCMで流れたナレーション。
当時人気のあった時代劇「子連れ狼」をモデルにしており、落語家の笑福亭仁鶴が出演した。
子供が「ちょっと待って」というときに、「三分間、待つのだぞ!」と真似した返しで、「じっと我慢の子であった」といって笑いをとっていた。
CMのセリフにあった「三分間待つのだぞ」もセットで人気だった。
実年
読み方
じつねん
意味
1985年に当時の厚生労働省が公募して決定した、50歳代・60歳代の年齢層のこと。
高齢化社会の進展にともない、定年を過ぎて新たな目標を見いだすための呼び名だが、一般に定着しなかった。
官庁用語として使用された。
失楽園する
読み方
しっらくえんする
意味
不倫のこと。
1997年に放送されたドラマ「失楽園」の流行からきている。
大きな社会現象を巻き起こし、最高視聴率27.3%を記録した。
シティボーイ
読み方
してぃぼーい
意味
都会風の流行を身につけた若い男性。
ファッションや趣味、価値観において都会的なこと。
1970年代に流行した。
そうなりきれない、垢抜けない男性を馬鹿にする意味でも使われた。
~してちょんまげ
読み方
~してちょんまげ
意味
お願いするときの語尾に使うギャグ。
とんねるずの木梨憲武のギャグ「許してちょんまげ」からきている。
小松政夫のニュアンスに影響されて生まれたギャグ。
派生的に「教えてちょんまげ」といった使い方をする。
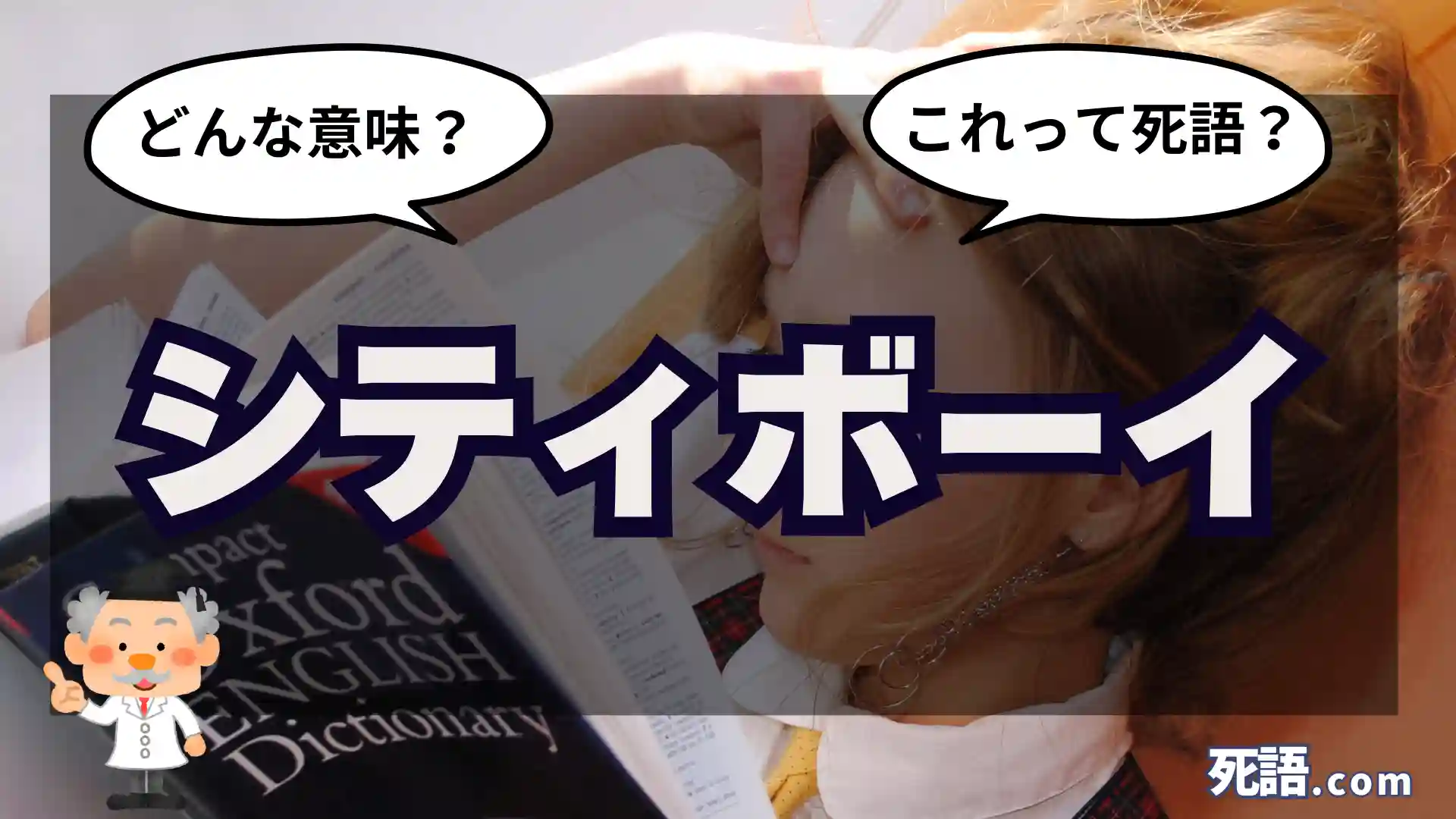
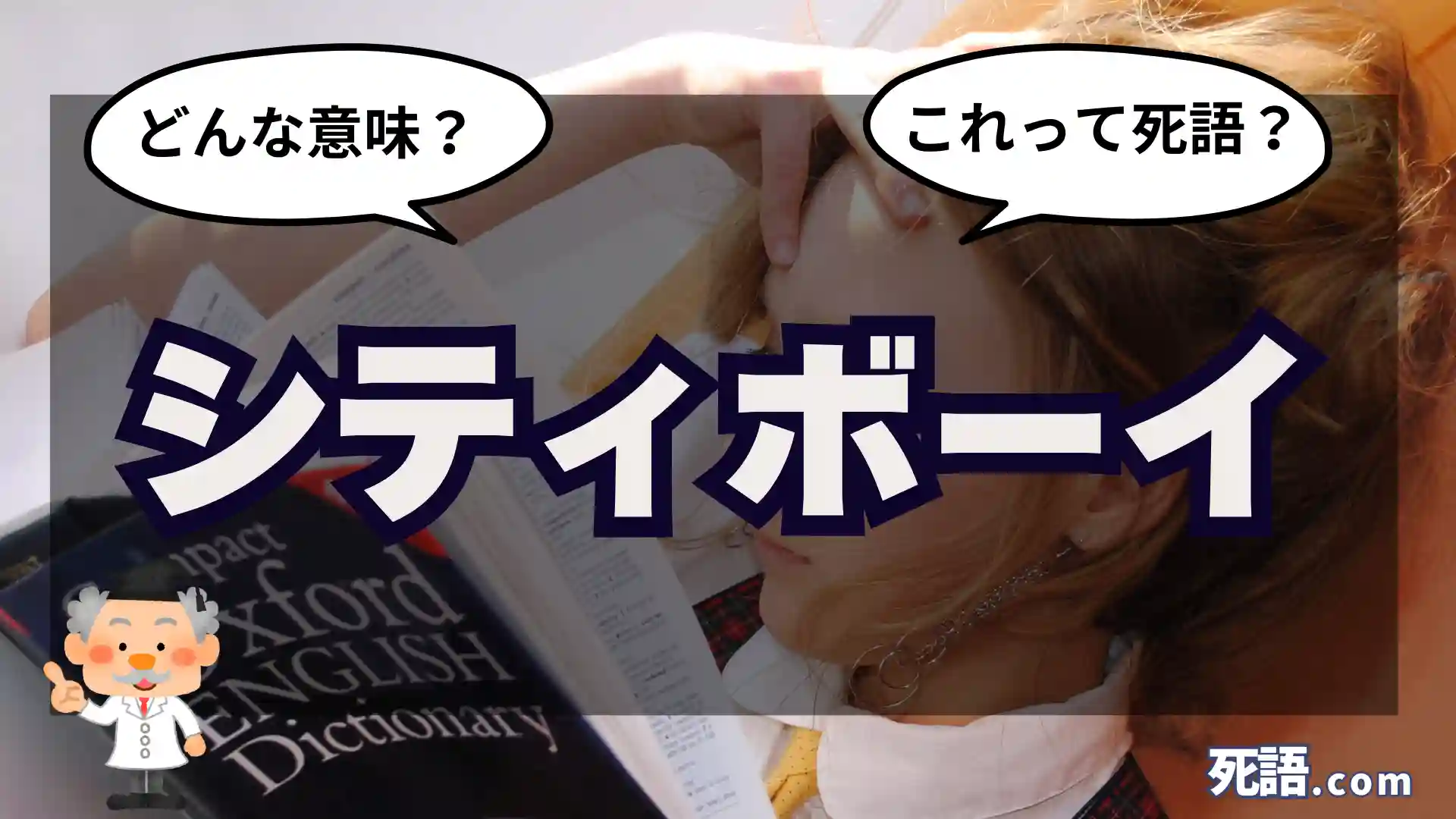
「しな」~「しの」で始まる死語一覧
「しな」~「しの」で始まる死語の一覧です。
シナチク
読み方
しなちく
意味
メンマのこと。
シナチクという言葉は、中国(支那)が原産の麻竹を使用していることに由来する。
「支那」という言葉が中国の蔑称とされ、死語になった。
「支那」の語源は欧米の「China」と同じ、紀元前3世紀末に中国を統一した秦が由来とされる説が有力。
シノラー
読み方
しのらー
意味
1990年代に人気だった篠原ともえさんのファッションを真似た女子のこと。
人気歌手の安室奈美恵を「アムラー」と読んだのと同じ当時の流行。
シノラーの特徴
- 前髪を横一直線に切る
- チープなおもちゃの腕輪や指輪をたくさんつける
- 子供っぽい雰囲気の服装
- 「~ですぅ」「キャッキャッ」といった幼い言葉使いや仕草
篠原ともえは、デビュー当時から衣装を全て自作していた。
現在、ファッションデザイナーとして活躍している。
「しは」~「しほ」で始まる死語一覧
「しは」~「しほ」で始まる死語の一覧です。
しばったるぞ
読み方
しばったるぞ
意味
相手を威嚇したり、脅したりする際に使われた俗語。
字引
しびれる
読み方
しびれる
意味
電気が走るような感動。
1960年代に音楽ファン文化から発生した表現。
興奮や感動で、体が麻痺するような感覚を比喩的に表現した。
渋カジ
読み方
しぶかじ
意味
1980年代後半のバブル経済期に発生した、渋谷を中心としたファッションカルチャー。
渋谷区、港区、世田谷区など山の手線沿線の学校に通う高校生から発生した。
アメリカンカジュアルを基調としつつ、渋谷のストリートカルチャーを反映したミニマルデザインが特徴。
渋カジの特徴やアイテム
- 「紺ブレ」
- 「吉田栄作ヘア」
- 「カシミヤのセーター」
- 「ミニのタイトスカート」
- 「モカシンなどの靴」
- 「インポートの革のコート」
- 「アヴィレックス」のフライトジャケット
- 「ヘインズ」のTシャツ
- 「リーバイス」の「501」(ジーンズ)
- 「レッドウィング」のエンジニアブーツ
- 「ルイヴィトン」のバッグ
ニルヴァーナやパールジャムなどのシアトル発のバンドの、反権威主義的な音楽「グランジ」などの影響を受けながら、1990年代の古着ブームにつながっていった。
しぶちん
読み方
しぶちん
意味
ケチること。またはその人。
蔑称。
もとは関西の言葉。
味覚の「渋い」から派生した語。
渋谷系
読み方
しぶやけい
意味
1990年代の音楽シーンで、サンプリング技術と、多ジャンルをミックスさせた、アートポップムーブメント。
東京の渋谷を発信地として流行した。
「フリッパーズ・ギター」や「ピチカート・ファイヴ」、「ORIGINAL LOVE」が代表的アーティスト。
1960年代から1970年代にかけての音楽知識と、最新カルチャー理解を合わせ持つ、「センス・エリート」と呼ばれる若者たちから発信された。
ジベタリアン
読み方
じべたりあん
意味
1990年代の、コンビニエンスストアの駐車場や、公共の道路の「地べた」に直接、座り込む若者のこと。
社会問題化した。
当時のストリートカルチャーの影響も受け、コンビニ前や階段、電車の床など、場所を選ばず地べたに座り込んでいた。
2000年代にはなくった。
「しま」~「しも」で始まる死語一覧
「しま」~「しも」で始まる死語の一覧です。
シミーズ
読み方
しみーず
意味
胸から腿までを覆うワンピース型の肌着のこと。
キャミソールのような肩紐付きの筒型デザインが一般的。
フランス語の「chemise」に由来し、亜麻(あま)製の下着を意味するラテン語、「カミシア(camisia)」が語源。
男性用はワイシャツに進化した。


シミチョロ
読み方
しみちょろ
意味
スカートの裾から、シミーズがチョロリとはみ出して見えてしまうこと。
女学生の隠語。
1950年代から使われていた。
「シミチラ」ともいう。
占子の兎
読み方
しめこのうさぎ
意味
「しめた!」という意味。喜ぶときに使う。
物事がうまく運んだときに使う江戸時代からの洒落言葉。
使い方
占子の兎だな、株価が急騰しているぞ
しめしめ
読み方
しめしめ
意味
じぶんの思いどおりになって、ひそかに喜ぶときに使う。
「しめ」は「しめた」の略。
下北マンボ
読み方
しもきたまんぼ
意味
映画『麗しのサブリナ』でオードリー・ヘップバーンが履いていた、サブリナパンツをモチーフにしたオリジナルパンツ。
細身で派手なプリント柄だった。
1960年代頃に東京・下北沢のENNYというお店で販売されていた。
しもしも
読み方
しもしも
意味
「もしもし」の倒語。
じもつう
読み方
じもつう
意味
地元に通じているという意味の若者言葉。
1990年代に使われていた。
関連語
- ジモッティー
- ジモッピー
- ジモティ
「しや」~「しよ」で始まる死語一覧
「しや」~「しよ」で始まる死語の一覧です。
じゃ。
読み方
じゃ
意味
フィクションの高齢者が語尾につける老人語。
現実の高齢者が使うことは、ほとんどない。
由来
江戸時代後半の上方語が起源。
芝居や俗文学で、老人や「生き字引」を表現する役割語として使われ始め、明治以降に小説や漫画、ドラマへと広まった。
シャーボ
読み方
しゃーぼ
意味
ゼブラ株式会社が1977年に開発した多機能ペン。
右回転でシャープペンシル、左回転でボールペンに切り替わる機構が特徴で、「1本で2本分」の機能性が支持された。
あえて話題にすることはなくなったが、現在も販売は続いていて、根強い需要がある。
ジャーマネ
読み方
じゃーまね
意味
「マネージャー」の文字順を入れ替えた倒語。
芸能・放送業界の業界用語で、タレントのマネジメント担当者
一般化して、学生間では部活動のマネージャーを指していう場合もある。
じゃーん!
読み方
じゃーん
意味
驚かせるようなものを見せるときに、効果音として口頭で言う擬声音。
じゃあ~りませんか
読み方
じゃあ~りませんか
意味
吉本新喜劇のチャーリー浜が考案したギャグ。
黒縁眼鏡にネクタイ姿がトレードマークで、この語尾が「海外かぶれのキザ男のキャラクター」を強調していた。
1991年にサントリーの栄養スナック「ポケメシ」のテレビCMで使用され、一躍全国的に有名になり、第8回日本新語・流行語大賞で年間大賞に選出された。
語源・由来
起源については、チャーリー浜の師匠と慕っていた大村崑の口癖だったという説がある。
ジャイケル・マクソン
読み方
じゃいけるまくそん
意味
知ったかぶりがマイケル・ジャクソンを言い間違えた語。
1980年代に使われた。
2005年から2009年にかけて、同名のバラエティー番組が放送された。
番組名の由来は、初代プロデューサー・新堂裕彦の母親が、「マイケル・ジャクソン」を「ジャイケル・マクソン」と言い間違えたエピソードから。
放送前から、この語はあった。
社会の窓
読み方
しゃかいのかど
意味
意図せずズボンの前ボタン・ファスナーが、はずれていること。
語源・由来①NHKラジオ番組からの由来説
1948年(昭和23年)から放送された、NHKラジオ番組『インフォメーションアワー・社会の窓』に由来する説がある。
社会問題やその裏側を探る番組内容で、「普段見られない部分が見える」という意味から。
語源・由来②学校でのエピソード説
昭和27年頃、中学校の社会科教師が、ズボンのファスナーを開けっぱなしにしていたのが由來という説がある。
徒が「また社会の窓が開いている」と冗談めかして言ったことが広まり、この表現が定着したとされる。
シャカリキに
読み方
しゃかりきに
意味
懸命になった何かに取り組むこと。
1950年から使われている流行語。
当初は平仮名だったという説があるが、1955年の時点でカタカナで使われていることがわかっている。
「はっは、生意気いわずに、とにかくオトナシくついてくればんだよ。君たちのあのシャカリキの練習ぶりに、御老体すっかり感激しちゃってるんだから」
由来として仏教の釈迦力を語源とする説があるが、戦後の流行語ということと、もともと釈迦力という言葉はないことから、疑問が持たれている。
しゃかりき
○川崎洋『流行語』(昭56・11毎日新聞社)-に○上田朝一「しゃかりきに―認知未了のコトバ」(『日本語』21-7(昭56・8)
引用:佐藤喜代治 編『講座日本語の語彙』別巻 (語彙研究文献語別目録),明治書院,1983.11. 国立国会図書館デジタルコレクション
シャキーン
読み方
しゃきーん
意味
驚かせるようなものを見せるときに、擬声音として使われた。
目覚めの爽快感や突然のひらめきを表現する場合もある。
シャギー
読み方
しゃぎー
意味
毛先をすくことで、不揃いにカットして軽さを出した髪型のこと。
1990年代に大流行した。
2000年代に入り、流行の復活のきざしがある。
ジャケ買い
読み方
じゃけばい
意味
CDや本のジャケットのデザインだけで、中身を確認せずに、インスピレーションで購入すること。
サブスクリプションサービスがなかった時代のカルチャー。
シャコタン
読み方
しゃこたん
意味
車高を極端に低く改造した自動車のこと。
暴走族の文化。
1980年代には違法改造車が大量に発生した。
1995年の規制緩和により、一定の基準内での車高調整が合法化された。
1990年代以降はローダウンと表現する場合が多い。
写真機
読み方
しゃしんき
意味
カメラのこと。
明治から写真機の名称で使われ始め、一般にカメラの名称が使われ始めたのは、確認できる限りで1917年頃から。
カメラは高級品で趣味性が高かったことから、昭和まで写真機という名称は使われていた。
読み方
じゃじゃうま
意味
夫や親や目上の人などのいうことを聞かない、わがままな気性の激しい女性。
しゃしゃる
読み方
しゃしゃる
意味
人が分を越えて厚かましく差し出ること。
「しゃしゃりでる」の略。
でしゃばる。
若者言葉で「調子に乗る」という意味もある。
ジャストミート!
読み方
じゃすとみーと
意味
答えや考えが一致する事。
日本TVの福澤朗アナが使っていた。
元は野球の会心の当たりのことで、野球解説者の名言から広まった。
社畜
読み方
しゃちく
意味
会社に飼い慣らされた家畜のようなサラリーマンのこと。
昭和の時代は経済が神格化され、サラリーマンは企業戦士と呼ばれて、休日出勤や深夜残業をいとわず働いていた。
しかしバブル崩壊によるリストラの断行など、終身雇用の神話が崩壊して、社会的な価値観が転換。
共同体への帰属心が弱まり、個人の利益が優先される時代に入って生まれた言葉。
現在はライフワークバランスが優先される時代になった。
鯱鉾張る
読み方
しゃちほこばる
意味
正確には「いかめしく構える」、「緊張して体がこわばる」という意味だが、俗語としては「図々しい」という意味もある。
「しゃっちょこばる」ともいう。
語源
「しゃちこばる」という表現が先。「さしこわる」からの変化とされる。
「さしこわる」は「差強」と書き、いかめしく構える、威厳をつくる、いばって見せるという意味。
「鯱鉾張る」の「鯱」は、「しゃち」を「鯱」と語源解釈して生まれた。
シャッポを脱ぐ
読み方
しゃっぽをぬぐ
意味
降参する。脱帽する。
語源
「兜を脱ぐ」を言いかえた表現。
シャッポは仏語で帽子のこと。
明治に入り、時代に合わせて生まれた語。
シャバい
読み方
しゃばい
意味
「ひ弱」「ダサい」「根性なし」「小心者」などを意味する言葉。
1980年代の不良文化で使われた。
一般社会を意味する「シャバ」が語源と考えられる。
2024年のギャル文化で復活のきざしがある。
ジャパゆきさん
読み方
じゃぱゆきさん
意味
1980年代に、東南アジアから日本に出稼ぎにきて、風俗産業に従事していた女性のこと。
不景気と各種法改正によって、衰退した。
日本の開国後に大陸に出稼ぎに行って、性風俗産業に従事した女性を指す「からゆきさん(唐行きさん)」という語から、日本に働きにきた外国人女性を「ジャパゆきさん」といった。
悪質業者のもとで働いていた「ジャパゆきさん」もいた。
一方で「からゆきさん」は長崎県の島原半島や、熊本県の天草出身者が多かった。
搾取されるばかりではなく、花魁のように、身請けされることもあった。
参考:
論文|ある「からゆきさん」の語りからみる女性の経験とグローバル・ヒストリー|嶽本 新奈|J-STAGE
ジャパンアズナンバーワン
読み方
じゃぱんあずなんばーわん
意味
1980年代に流行した、日本の経済力を自賛するスローガン。
元はエズラ・ヴォーゲル博士の書いた同名の書籍。
戦後日本の成功を分析し、アメリカへの教訓として提示しており、日本の教育、政府の指導力、企業の一体感などを称賛した。
日本語版は70万部を超えるベストセラーになり、スローガン化した。
1990年代に入るとバブル崩壊と、金融至上主義によるグローバル化で、物作りを武器とした日本の社会情勢は大きく変わった。
写メ
読み方
しゃめ
意味
携帯電話で撮影した写真をメールで送ること。
転じてデジタル写真の優位性が強調され、デジタル写真全般を写メと呼ぶようになった。
デジタル写真が標準化したことで、写メは死語になった。
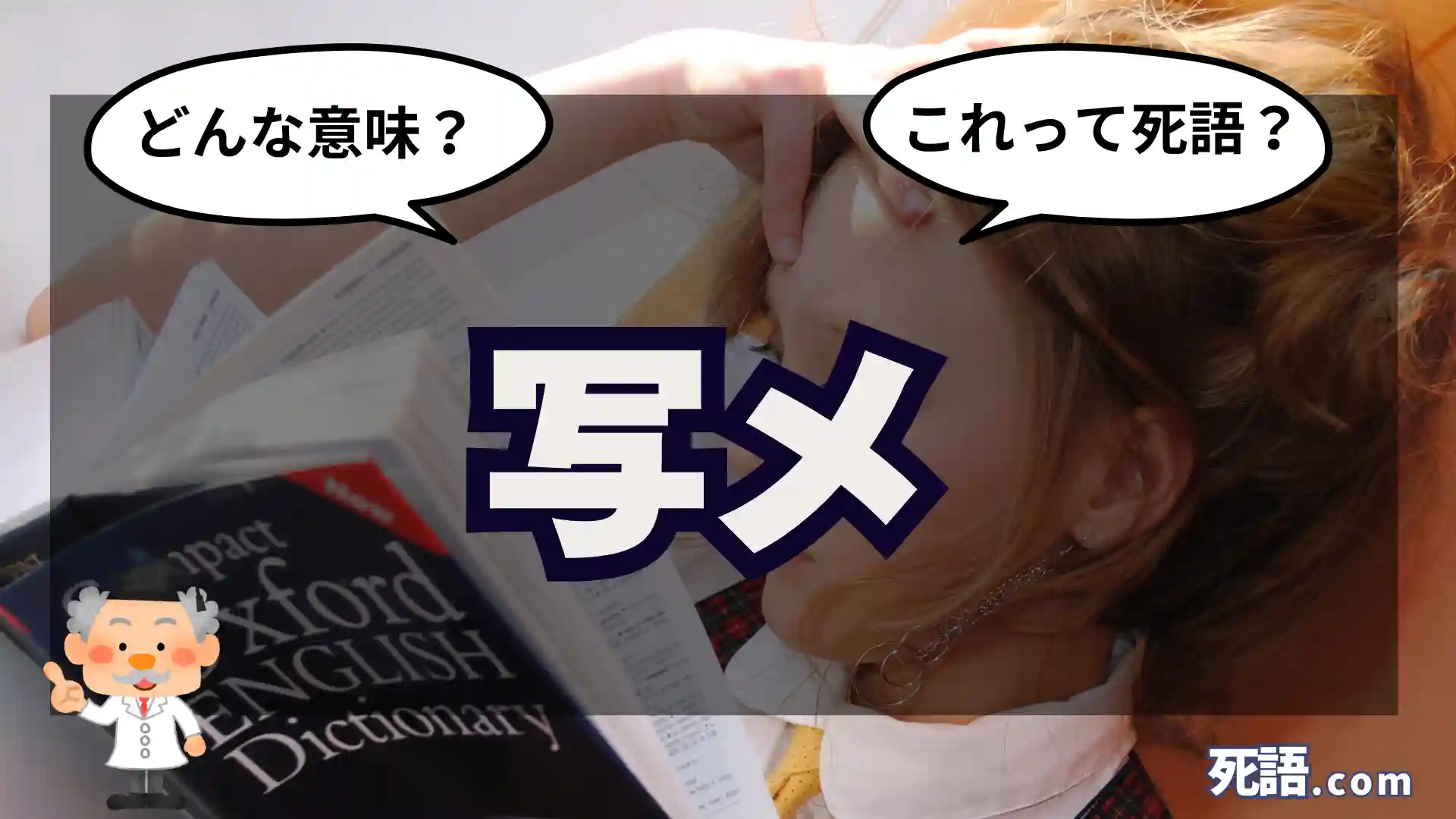
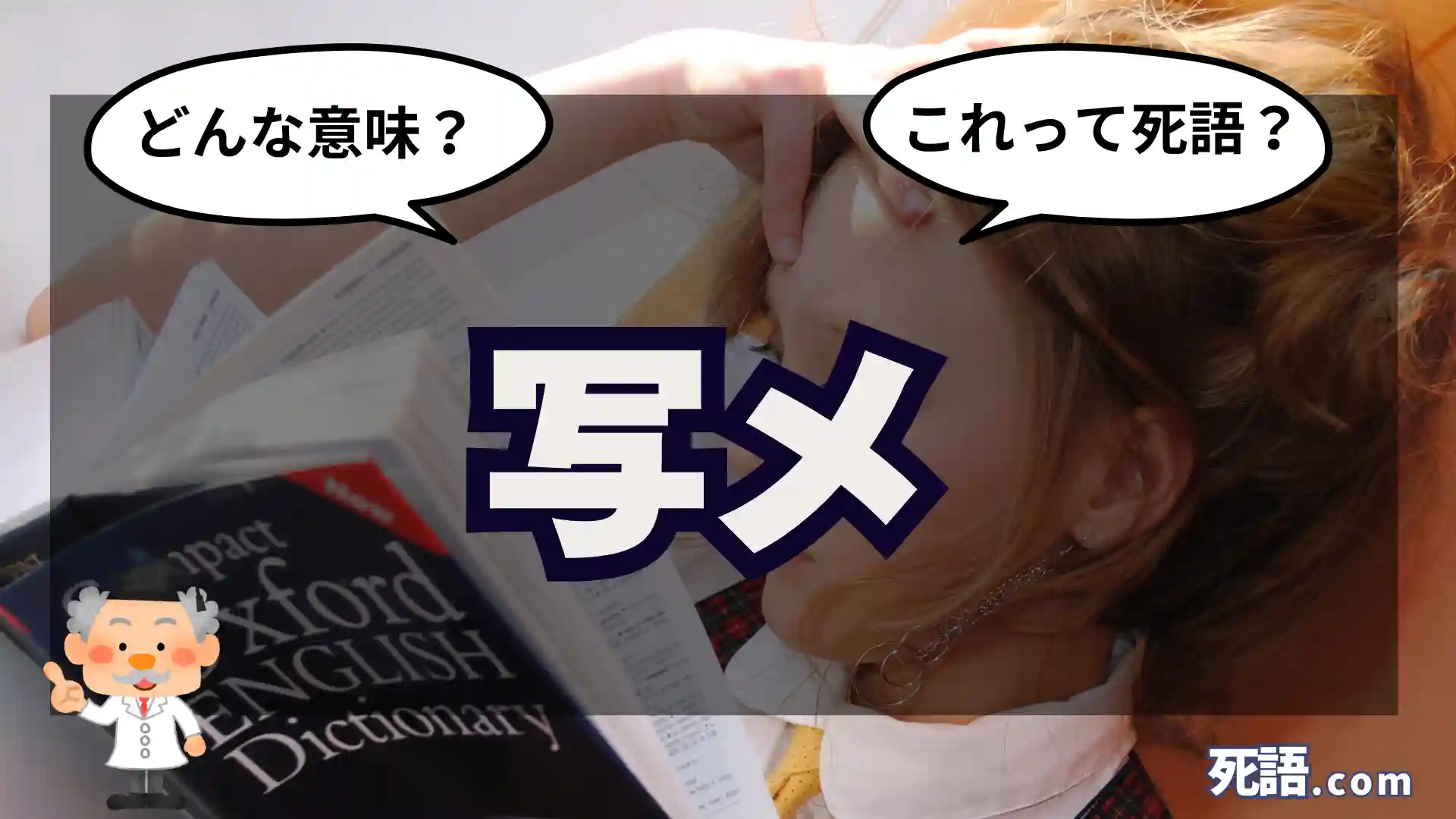
ジャミラ
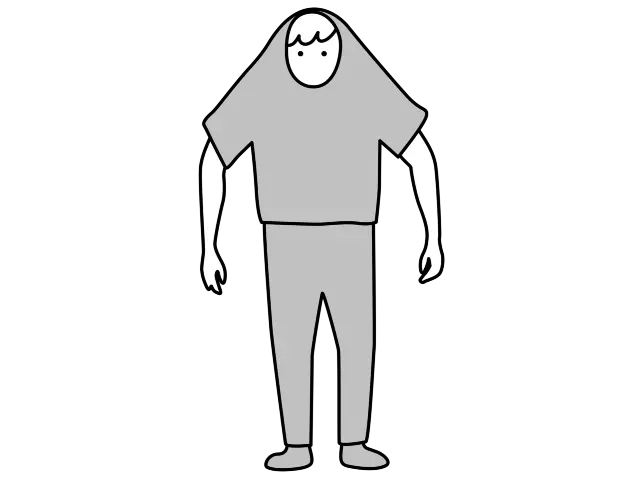
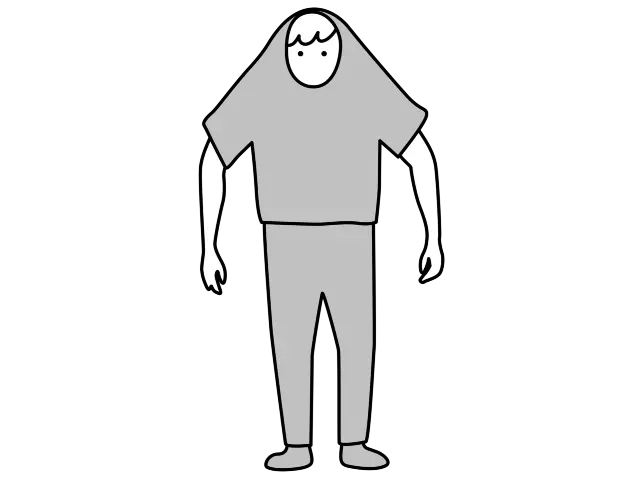
読み方
じゃみら
意味
ブレザーなどを、頭にかぶってウルトラ怪獣ジャミラの真似をすること。
ジャミラは、特撮テレビドラマ『ウルトラマン』をはじめとする、「ウルトラシリーズ」に登場する架空の怪獣。
斜陽族
読み方
しゃようぞく
意味
戦後、華族令が廃止されて、没落した華族のこと。
没落した旧上流階級。
1948年の流行語。
語源
太宰治の小説『斜陽』によって広まった表現です。
作品の全体で、静かに衰退してい悲しみを描写した。
しゃらくせえ・しゃらくさい
読み方
しゃらくせえ・しゃらくさい
意味
差し出がましい、またはそのような態度を指す言葉です。
邪魔くさい、面倒だ
使用例 あーもう、しゃらくせえ!
語源
「お洒落(おしゃれ)」が転じて「しゃら」になったという説や、遊女を「しゃら」と呼んでいたことに由来するという説があります。
ジャリタレ
読み方
じゃりたれ
意味
子供タレントのこと。蔑称。
砂利(ジャリ)は戦前から使われている、寄席やテキヤの隠語で、子供のこと。
タレはタレント。
実力のある子供タレントが増えて死語化した。
以下の引用のとおり、1929年の書籍にも記載がある。
砂利 じゃり 犯
子供のことをいふ
ジャリっ子
読み方
じゃりっこ
意味
砂利(ジャリ)は戦前から使われている、寄席やテキヤの隠語で、子供のこと。
もともと「ジャリ」は蔑称だが、「っ子」とつなげて、愛称としても使う。
「じゃりんこ」ともいう。
シャン
読み方
しゃん
意味
美人のこと。
語源
ドイツ語で、「schön(美しい)」の変化した形。
旧制高等学校の学生のことばから一般に広まった。
昭和初期に流行語となり、多くの合成語ができた。
学生は原語に近い「シェーン」とも言っていた。
じゃんじゃんバリバリ
読み方
じゃんじゃんばりばり
意味
パチンコのマイクパフォーマンスの一節。
「さあ、どなたさまもジャンジャンバリバリ、ジャンジャンバリバリお出しください」
軍艦マーチとセットで店内に流れていた。
バリバリは、昔の出玉は金属のバケツに入れていて、バリバリと音を立てたことからとされる。
「射幸心を煽る」ため、現在は禁止されている。
ジャンパー
読み方
じゃんぱー
意味
ブルゾンのこと。
語源・由來
ブルゾンのこと。
元々は「頭からかぶる上着」を意味するイギリス英語「jumper」が由來。
本来はセーターやカーディガンを指す言葉。
1937年から使われ始め、1950年代以降に定着した。
一方、ブルゾンはフランス語起源。
現代のブルゾンは1937年の英国陸軍のジャケットを基にした、ゴルフ用のジャケットが原型。
祝言
読み方
しゅうげん
意味
結婚式のこと。
「結婚式の祝いの言葉」の意味は残っている。
重戦車
読み方
じゅうせんしゃ
意味
動きが遅いものの、迫力のあるたとえ。
曙太郎など。
十八番
読み方
じゅうはちばん
意味
最も得意な芸や技能のこと。
おはこ。
語源
歌舞伎俳優の七代目団十郎が市川流の得意とする芸が、1832年に発表した『歌舞伎十八番』だったことが由来。
おはこの語源は、「お」は丁寧ないし尊敬の接頭語、「はこ」は「箱書き付き」の下略とされる。
「箱書き付き」は折り紙付きと同じで、美術品などに鑑定書が付いていること。
鑑定書が付いているほど確かな得意芸という意味。
「おはこ」に「十八番」の字をあてるようになった。
10万円、7万円、5万円
読み方
じゅうまんえん、ななまんえん、ごまんえん
意味
「がっちり買いまショウ」というテレビ番組の、「5万円、7万円、10万円運命の分かれ道」というフレーズ。
買い物ゲームで、決められた予算内で、かつマイナス4000円を上回る買い物ができた場合に、買った品物をもらえた。
16文キック
読み方
じゅうろくぶんきっく
意味
ジャイアント馬場のプロレス技。
ロープで跳ね返ってきた相手選手の顔面を、突き出した足の裏で前蹴りする。
多くの子供が真似をした。
語源・由来
ジャイアント馬場の靴サイズ、米国規格サイズ16を、「1文=2.4cm」換算した、メディアの誤報が定着した。
10回10回クイズ
読み方
じゅっかいじゅっかいくいず
意味
特定の言葉を10回を言ったあとで、言い間違えしやすい問題をだして、引っかけるクイズ。
「ミリンって10回言って……、ミリン、ミリン、……ミリン、……鼻の長い動物 なぁーんだ? ……キリン!」など。
語源・由来
1987年にニッポン放送の「鴻上尚史のオールナイトニッポン」で取り上げられたのが最初。
翌年の1988年1月には、同番組初の本「10回クイズちがうね」が出版されて流行した。
フジテレビの「笑っていいとも!」など、そのほかの番組でも取り入れられた。
ジュクが待っている
読み方
じゅくがまっている
意味
ジュクは新宿のこと。
最後には新宿に帰るというフレーズ。
呪女
読み方
じゅおんな
意味
別れた男の事をいつまでも根にもっている女性のこと。
2000年に流行したホラー映画「呪怨」の言葉遊びとして、同じ時期に使われていた。
ジュリアナ女
読み方
じゅりあなおんな
意味
バブルの象徴とされる、1990年代初頭の巨大ディスコ「ジュリアナ東京」で、お立ち台で踊る女子のこと。
ボディコン姿で、通称「ジュリ扇」という羽毛扇を振って踊っていた。
ジュリアナ東京
読み方
じゅりあなとうきょう
意味
ジュリアナ東京は1991年から1994年まで東京都港区芝浦に存在した、最大収容人数2,000人を誇る巨大なディスコ。
「お立ち台」や、通称「ジュリ扇」という羽付き扇子、ワンレン・ボディコンの女性たちが踊っていた。
バブル期の象徴とされているが、実際は バブル崩壊が始まった時期だった。
専属DJのジョン・ロビンソンのMCの「ジュリアナス〜トキオ〜!」というフレーズも有名。
経営不振や、バブル崩壊の影響で1994年に閉店した。
ジュリ扇
読み方
じゅりせん
意味
バブルの象徴とされる、1990年代初頭の巨大ディスコ「ジュリアナ東京」で、お立ち台で踊るボディコンのが降っていた扇子。
蛍光色の羽毛扇だった。
瞬間貴族
読み方
しゅんかんきぞく
意味
レンタル品などで、貴族のような優雅な時間を、一時的に楽しむこと。
レンタルのワインセットなどのアイテムを使う。
瞬間湯沸し器
読み方
しゅんかんゆわかしき
意味
すぐにカッとなる、短気な人を指す俗語。
スイッチオンでお湯がでる給湯器がめずらしかった時代に、よく使われた。
純喫茶
読み方
じゅんきっさ
意味
アルコール類を提供しない、コーヒーや軽食を中心とした喫茶店のこと。
1950年代から1960年代にかけて流行した。
背負子
読み方
しょいこ
意味
束ねたまき等を、背負うための道具。
地域によって呼び名が異なり、セデ、セーハシゴ、セータ、セタンマなどと呼ばれる。
傷痍軍人
読み方
しょういぐんじん
意味
第二次世界大戦で負傷した旧日本軍の軍人のこと。
戦時下は名誉の負傷として扱われたが、アメリカのGHQの統治による価値観の転換で、不遇の扱いを受けた。
軍人恩給は廃止され、働くこともままならない人々は困窮した。
故郷のために戦ったにも関わらず、戦後の世間の軍部憎しの感情から、白い目で見られることも多かった。
終戦から18年たった昭和38年に、戦傷病者特別援護法が成立した。
参考:
日本のために戦い、犠牲となったのに…戦後、過酷な境遇を生きた「傷痍軍人とその妻たち」|週刊現代|講談社
省エネルック
読み方
しょうえねるっく
意味
半袖のスーツのこと。
1979年の第二次オイルショックの際に、第1次大平内閣が提唱した。
東南アジアなど熱帯国のスタイルを参考にした。
大平正芳や羽田孜らの政治家が推進し、メディアも報道したが、普及しなかった。
のちにクールビズを考案した小池百合子が参考にした。
正月の餅が買える
読み方
しょうがつのもちがかえる
意味
師走に正月の餅が買えるかどうかで、経済的な困窮を表現する言葉。
非常に貧しい生活状況を指すために使われる。
使い方



こんな収入じゃ、正月の餅も買えないよ
少女変体文字
読み方
しょうじょへんたいもじ
意味
1980年代に爆発的に流行した、少女たちのあいだで使われた、「丸字」「まんが字」のこと。
丸っこく扁平な字体が特徴で、くわしく分析研究した、山根一眞による造語。
上手い
読み方
じょうずい
意味
見事な技術をたたえる形容詞。
文化放送の深夜ラジオからの発祥。
使い方



さすがの志ん生、黄金餅をきいたけど、上手いねえ
省線
読み方
しょうせん
意味
鉄道省の略称、またはその鉄道のこと。
鉄道「省」路「線」。
1920年から1943年まで鉄道に関する業務を管轄していた、国家行政機関。
国鉄と運輸省に分離後、運輸省は現在の国土交通省になった。
冗談はよし子さん
読み方
じょうだんはよしこさん
意味
「冗談はやめて」という意味の言葉遊び。
漫画「ジョーダンはよし子ちゃん!」からの派生。
1980年代に流行し、1990年以降はしばあくおやじギャグとして活用された。
ジョーダンはよし子ちゃん
読み方
じょーだんはよしこちゃん
意味
「冗談はやめて」という意味の言葉遊び。
漫画「ジョーダンはよし子ちゃん!」で普及した。
1980年代に流行し、1990年以降はしばあくおやじギャグとして活用された。
冗談はよしのすけ
読み方
じょうだんはよしのすけ
意味
「冗談はやめて」という意味の言葉遊び。
漫画「ジョーダンはよし子ちゃん!」からの派生。
1980年代に流行し、1990年以降はしばあくおやじギャグとして活用された。
省電
醤油顔
読み方
しょうゆがん
意味
あっさりとした日本的な顔立ちのこと。
特徴
- 彫りが浅い
- 切れ長の目
- 鼻筋が通っている薄い唇
- 一重まぶたまたは奥二重
- 小顔
- なめらかな輪郭 など
しょってる
読み方
しょってる
意味
うぬぼれが強いことを、からかうときに言う語。
語源・由来
「自負している」の変化。
使い方



おれのことを女の子がほっといてくれないんだよ
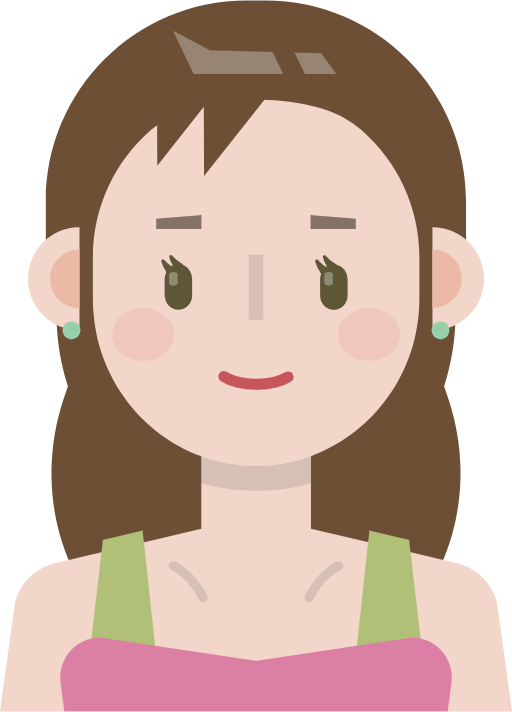
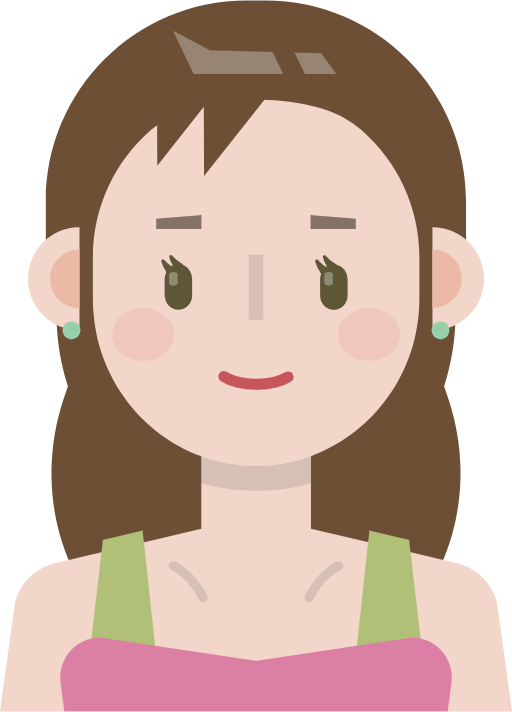
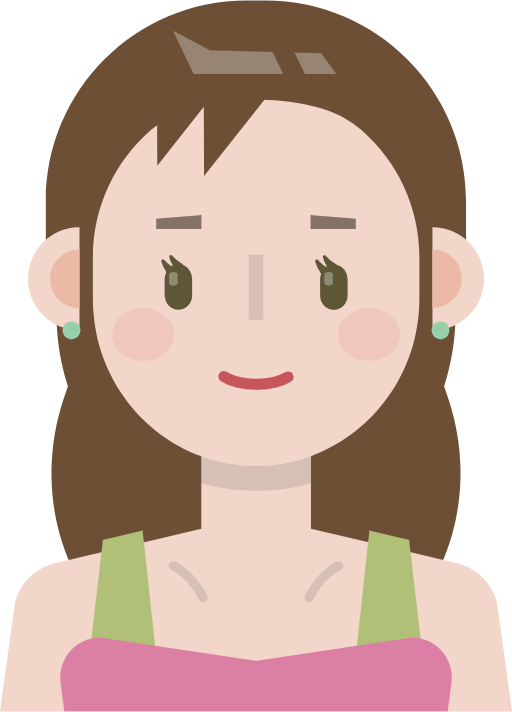
しょってる!!
ショッピ
読み方
しょっぴ
意味
昭和の時代に、名古屋で展開していたスーパーマーケットのこと。
名鉄ショッピから、ヤマナカ、桔梗屋、フィールと変遷した。
「しら」~「しろ」で始まる死語一覧
「しら」~「しろ」で始まる死語の一覧です。
白波
読み方
しらなみ
意味
盗賊のこと。
語源・由来
後漢末期の中国で、黄巾の乱の残党に由來する、
残党は盗賊集団になり、河西(現在の山西省)の白波谷(はくはこく)に立てこもって、略奪行為を行った。
日本に伝わると平安時代以降、「白波」が訓読みされて「しらなみ」となり、盗賊を意味する隠語として使われるようになった。
近代では「白浪」という当て字が用いられ、歌舞伎では「白浪物」として、『鼠小僧』『三人吉三』『白浪五人男』などの義賊が描かれている。
知らぬ顔の半兵衛
読み方
しらぬかおのはんべえ
意味
知っていながら知らないふりをすること。
語源・由来
戦国時代の名軍師・竹中半兵衛に由来。
織田信長の美濃攻略時に前田利家を欺いたエピソードが語源とされる。
半兵衛は敵の策略を見抜きつつも、とぼけて平然と振る舞い、逆にその状況を利用して勝利を収めた逸話が多く残されている。
資料を焼く
読み方
しりょうをやく
意味
資料の記載されたペーパーを、コピ-機でコピーすること。
語源・由来
トナーを焼き付けることからとされる。
シロガネーゼ
読み方
しろがねーぜ
意味
東京都港区白金エリアに住む富裕層の女性のこと。
2000年代初頭に流行した。
語源・由来
1998年に女性誌『VERY』編集者だった相沢正人が作った造語。
イタリア語「ミラネーゼ(ミラノっ子)」からきている。
白テープ
読み方
しろてーぷ
意味
1980年代の不良文化で、学生カバンの持ち手にビニールの白テープを巻くことで、「ケンカ買います」のサインにしていた・
赤テープは「ケンカ売ります」のサインだった。
白物家電
読み方
しろものかでん
意味
冷蔵庫や洗濯機のような、生活家電のこと。
テレビなどは黒者家電といわれた。
語源・由来
生活家電は、本体が白色筐体が多いことから。
「しわ」~「しん」で始まる死語一覧
「しわ」~「しん」で始まる死語の一覧です。
じわる
読み方
じわる
意味
「じわじわくる」を略した言葉で、最初は何も感じなかったが、後から面白さや感情がじわじわと込み上げてくること。
2015年に三省堂の「今年の新語」大賞を受賞し、SNSを通じて広まった若者言葉。
笑いや感動だけでなく、寂しさや怖さにも使われることがある。
シンガーソングライター
読み方
しんがーそんぐらいたー
意味
自ら作詞・作曲し、それを歌う音楽家のこと。
おもにポピュラー音楽において使われる。
作詞作曲した歌を自分で歌う商業歌手の意。作詞家・作曲家・編曲家と歌手が異なる形態が中心の流行歌・演歌が音楽芸能の殆どであった時代に冒頭のスタイルを取るフォークシンガーが登場し、ユーミンらがニューミュージックと呼ばれていた間、表題の呼称を使用した。現代の芸能音楽の特にセールスの大半を占めるロックではこの形態が多く、いちいち区別する事も無くなった。
語源・由来
1970年代初頭にアメリカで注目されたジェームス・テイラーらの活躍により普及した呼称。
1960年代までは、作詞と作曲を分業することが、ほとんどだった。
しんじらんない
読み方
しんじらんない
意味
自分の意見と合わないときや、驚いたときに使われるリアクション。
おもに日常会話で使われた。
新人類
読み方
しんじんるい
意味
1955年~1965年ごろに生まれた世代を指し、それまでになかった価値観や考え方を持った、当時の若者層のこと。
1980年代なかばに流行した。
高度経済成長期に育ち、消費意欲が高く、友達のような親子関係を築く傾向が注目された。
語源・由来
経済学者の栗本慎一郎が造語し、若者の新しい価値観を皮肉った表現から広まった。
心臓~
読み方
しんぞう~
意味
身の丈にあわないことや、厚かましさに対する表現。
使い方
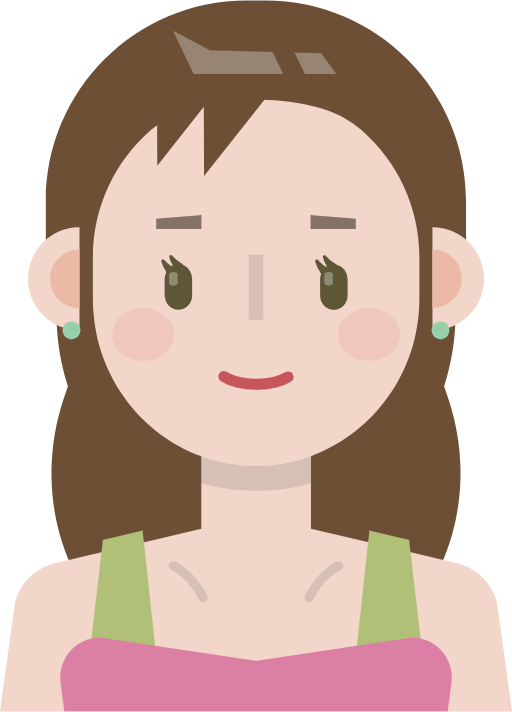
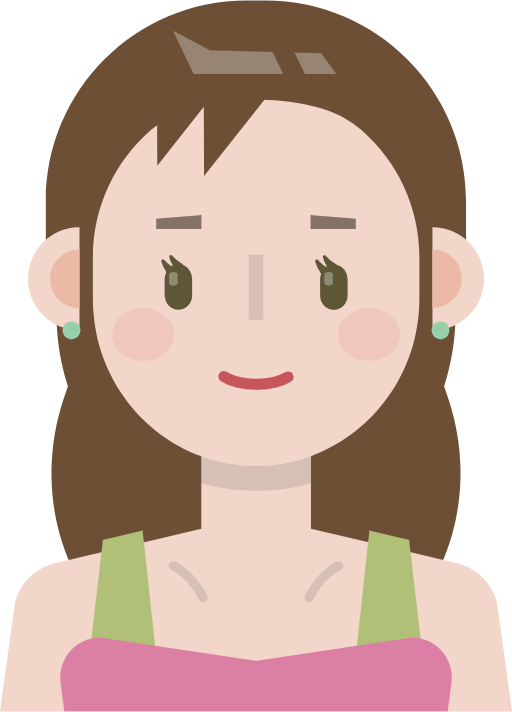
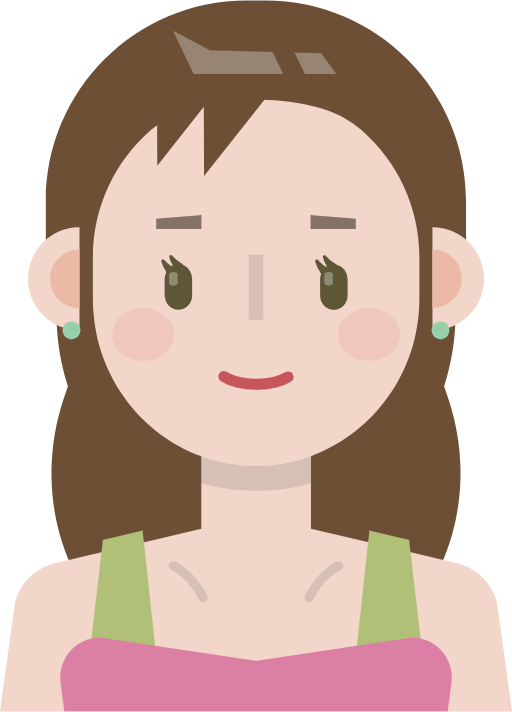
そっ、それって心臓~
慎太郎刈り
読み方
しんたろうがり
意味
1956年に流行したスポーツ刈りの一種で、前髪を長めに残したスタイル。
太陽族の若者などが真似していた。
語源・由来
作家の石原慎太郎原作の映画『太陽の季節』で、作家本人が出演して、髪型をしていたことから。
新聞によりますと……
読み方
しんぶんによりますと……
意味
1970年代の土曜夜10時にテレビで放送していた、『テレビ三面記事 ウィークエンダー』のフレーズ。
桂ざこばや、横山やすし、西川きよしが下世話な事件を紹介していた。
使い方



新聞によりますと、昼休みに田中さんが、佐藤さんのスカートをめくったそうです
しんぶんによりますと…
シンパ
読み方
しんぱ
意味
「シンパ」は日本では昭和初期に使われていた言葉で、「共産党員を資金的に援助する人」という意味の死語です。


「し」からはじまる死語まとめ
本記事では「し」からはじまる死語を紹介しました。
思わぬ発見や、懐かしい記憶とは出会えたでしょうか?
さあ、ほかにも数多くの死語があなたを待っています。
ぜひ、このほかの死語も楽しんでください!
人気の記事
タップできる索引