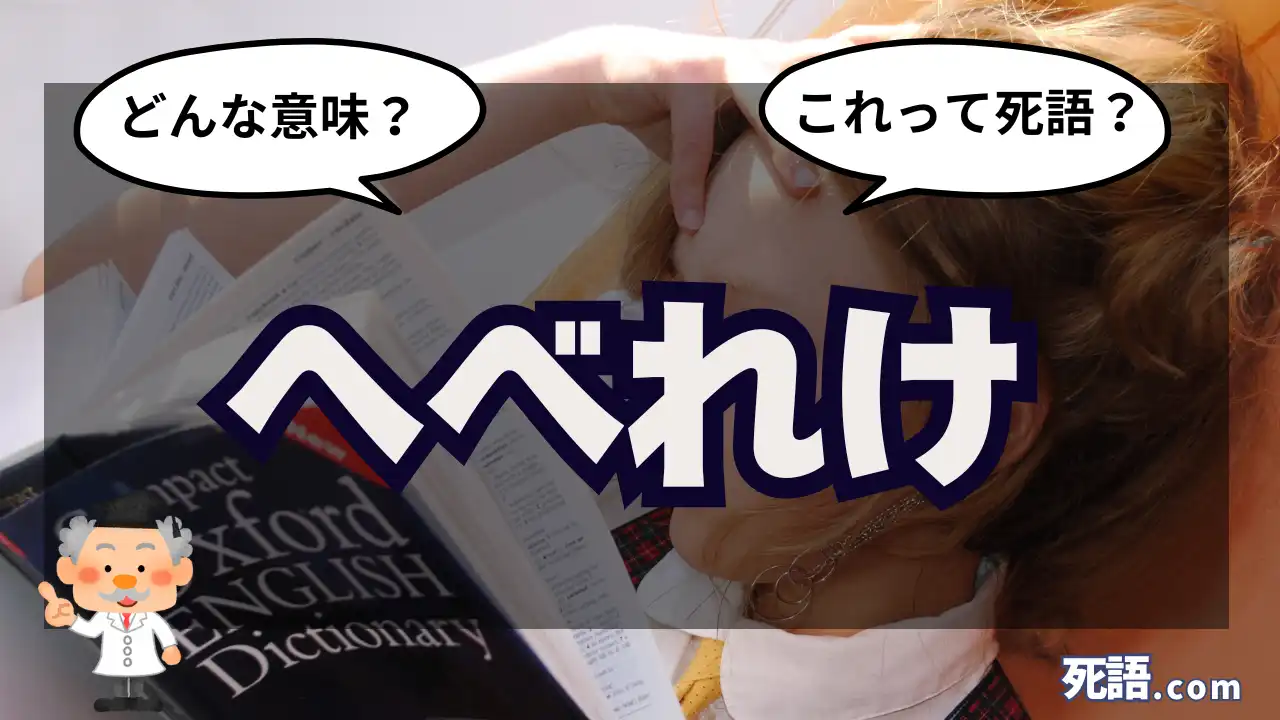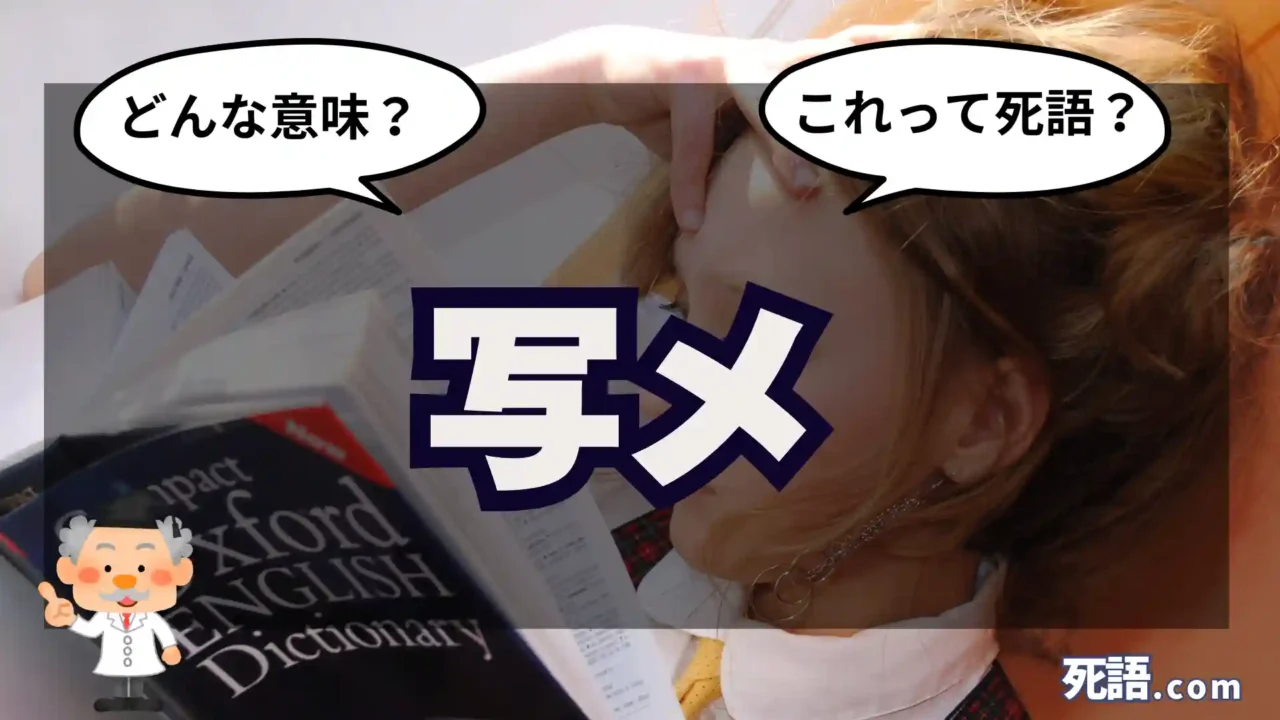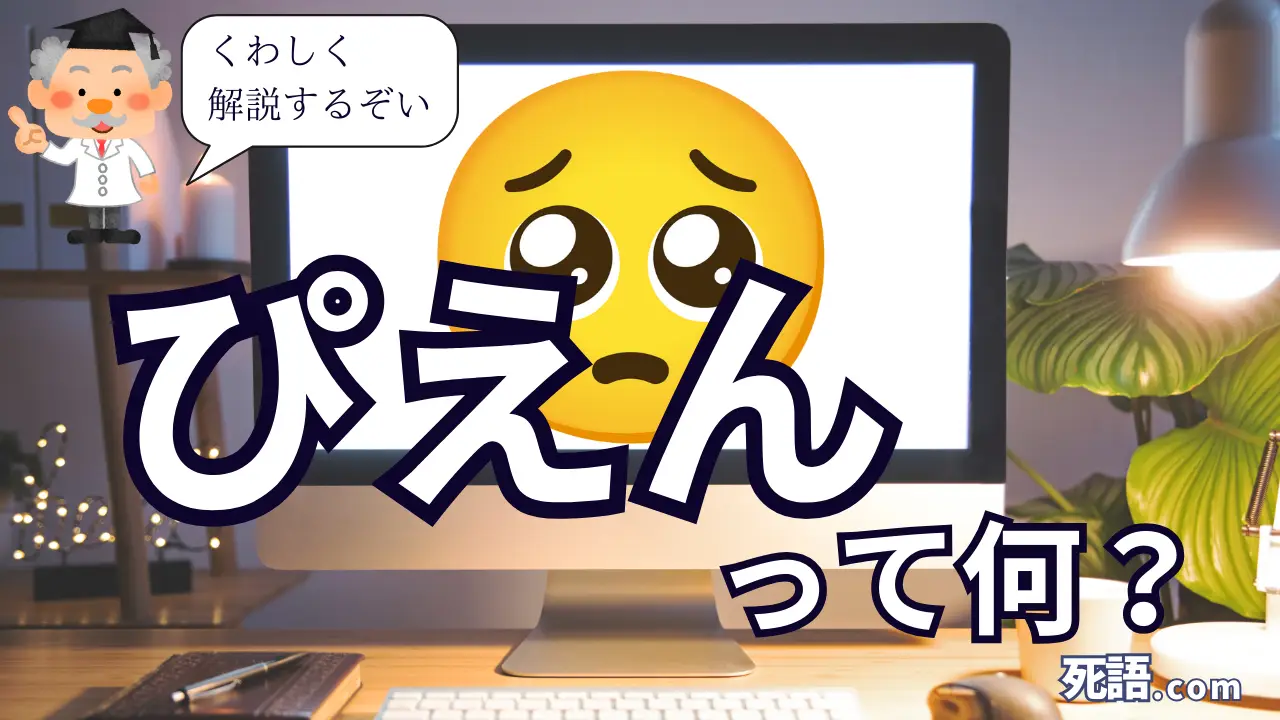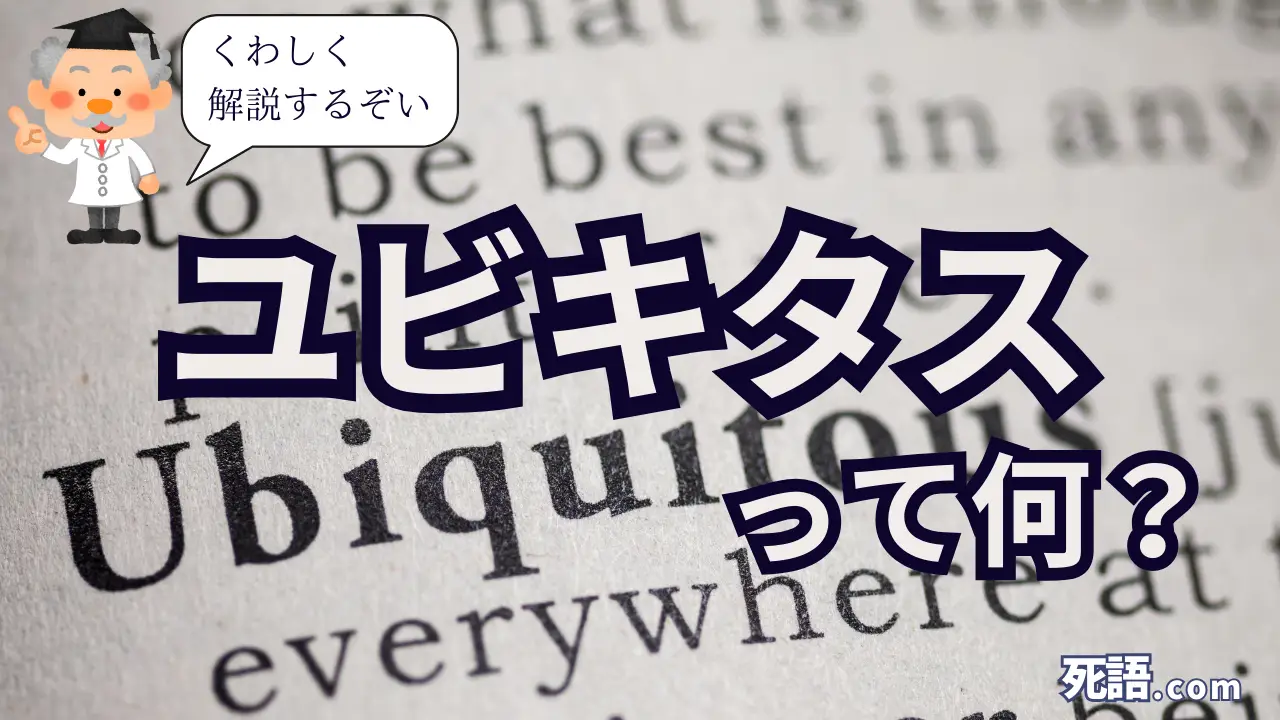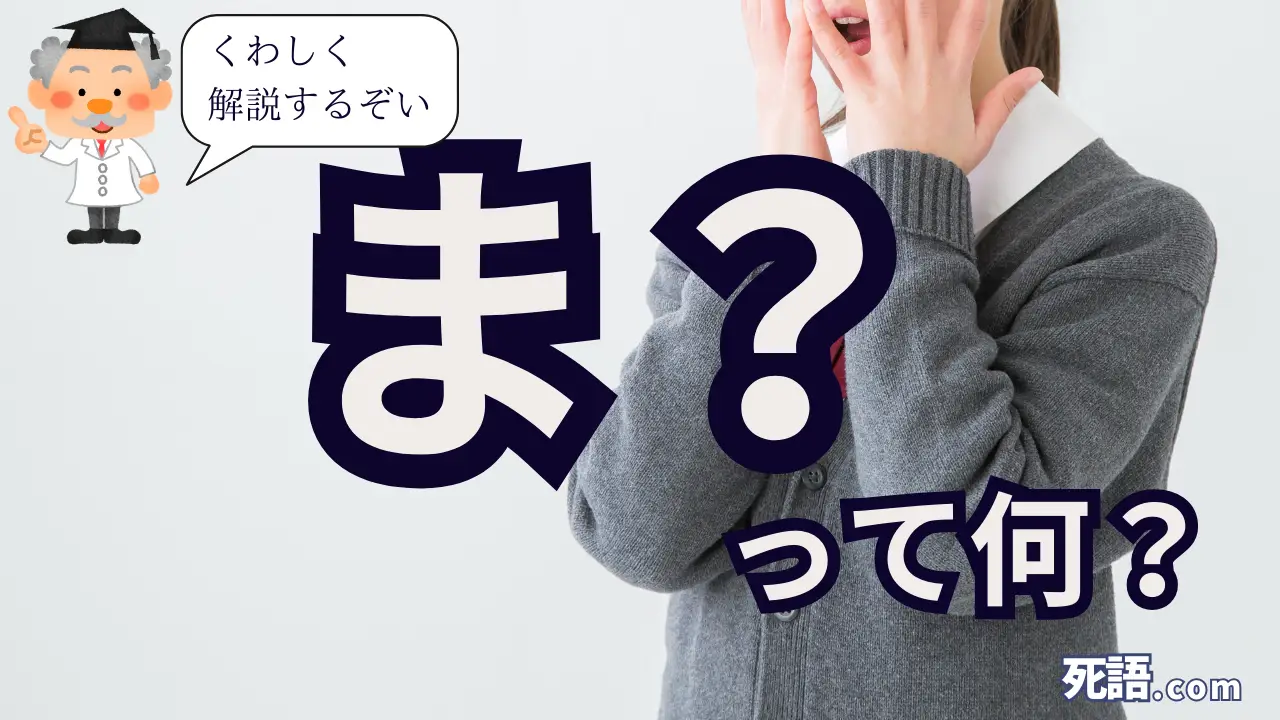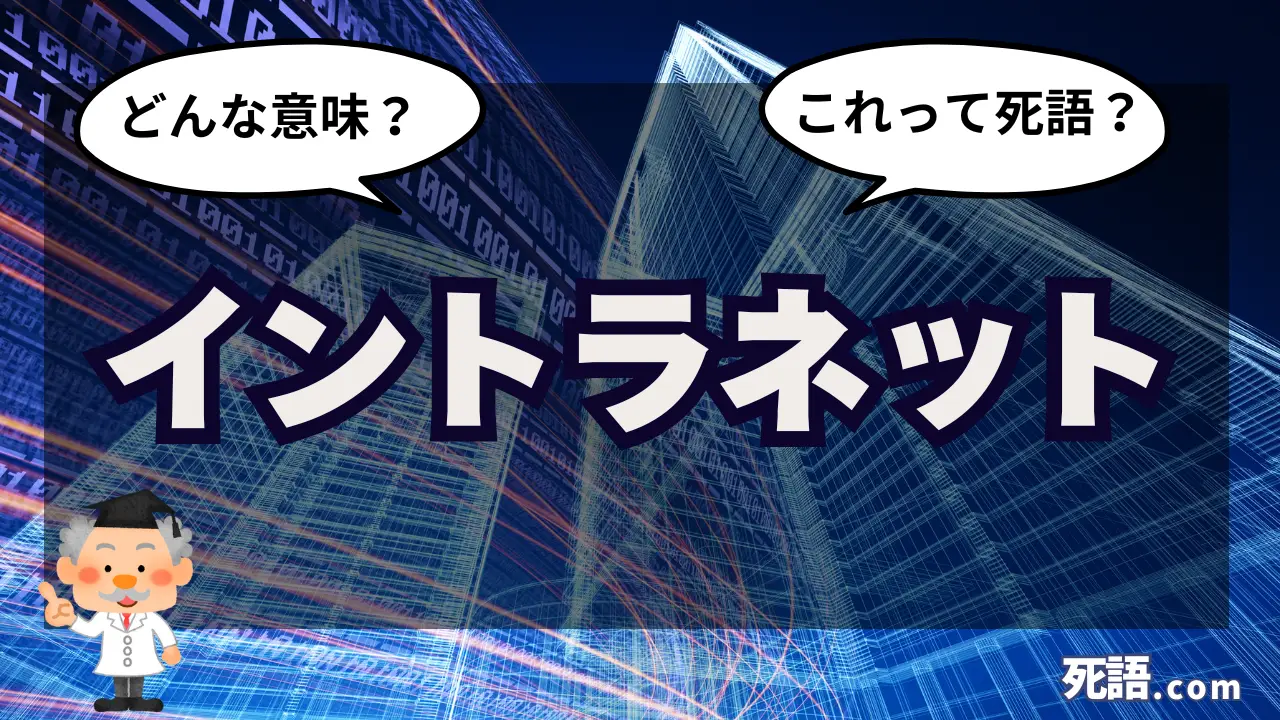「へべれけ」は「前後不覚に酔っぱらう」という意味です。
死語度は60%です。
語源はギリシア神話の「ヘーベのお酌」という説がありますが、もとは大正時代の木村鷹太郎の創作した説です。
オノマトペ(擬音語)の一つと考えられます。
本記事では「へべれけ」の意味を解説して、現代では死語なのかを考察します。
本記事のリンクには広告が含まれています。
タップできる索引
「へべれけ」の意味を解説
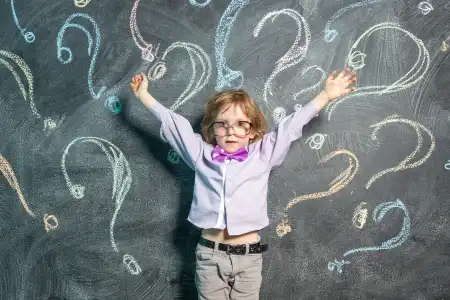
「へべれけ」の意味を解説します。
「へべれけ」の意味
「へべれけ」は「前後不覚に酔っぱらうこと」や、その状態をいいます。
「へべのれけ」という場合もあります。
記憶がなくなるほど酔った状態を「へべれけになる」といった使い方をします。
酔っぱらいそのものをいう場合もあります。
類義語に「グロッキー」ががあり、こちらは「グロッグおやじ」というあだ名の提督が「水兵に配給したラム酒」が語源になっています。
「へべれけ」の語源や由来を解説
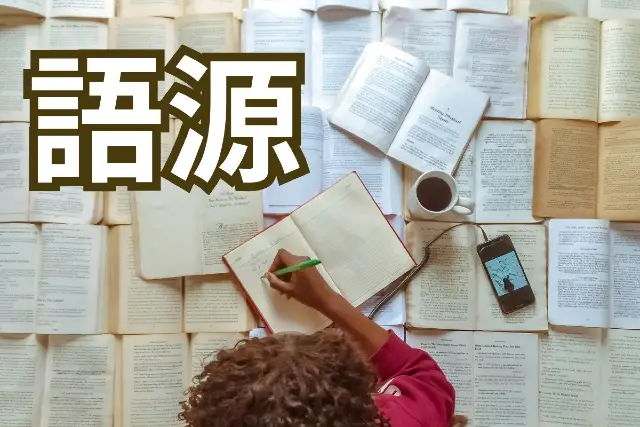
「へべれけ」の由来には2つの説があります。
- 単なるオノマトペ(擬音語)説
- 「ヘーベのお酌」を意味するギリシャ語「Hebe-erryeke」説
オノマトペ(擬音語)説
「へべれけ」に具体的な語源はなく、単なるオノマトペと考えることもできます。
オノマトペ(擬音語)とは、「むしゃくしゃ」や「しっとり」のように、本来は音がない、状態や質感、動き、性質を表現する言葉です。
古くは古事記にある「コラロ」、「トドロ」、「ソヨロ」のような、ヤマト言葉のオノマトペが使われていました。
また日本に漢語が入ってくると、オノマトペはより豊富になっていった歴史があります。
平家物語でも「むずと組み」、「どうと落ちる」、「能っ引く」、「ひょうと放つ」、「ざんぶ」といったオノマトペが使われています。
少なくとも明治時代には使われていた
調べると、少なくとも明治時代の1883年には、「へべれけ」という言葉が使われていたことが、わかります。
「ナァーに別に用ハなけれども今日ハ連中の御馳走に呼ばバれてお神酒澤山頂戴でゲンテ如此な言語 ヘベレケ 身体ぐでんぐでん大酩酊連も酔てハ指南に能ハモデゲス哩
「ヘーベのお酌」説は大正時代の木村鷹太郎の創作
「へべれけ」の語源は、「ヘーベのお酌」を意味するギリシャ語「Hebe-erryeke」という説があります。
1926年の木村鷹太郎が書いた『希臘羅馬神話』という本が最初で、この説自体が著者の木村鷹太郎の創作 です。
お酌のことをギリシア語でエレケという。ヘベレケをまた「ヘベのレケ」ともいうが、それはこの「ヘーベのお酌」ということらしい。 「ベレケに酔う」とは「ヘーベのお酌で酔う」と解すれば説明がつく。この説明は 木村鷹太郎氏が明治・大正の頃、日本文化とギリシア文化との類似を説いて狂人あつかいされた説の一つ である。
『希臘羅馬神話』は、ギリシャ・ローマの神話を, 日本や東洋の神話、伝説、民俗、言語と比べながら説明している本です。
この本にある「女神ヘーベ」の説明で、「へべれけ」とは 「ヘーベのお酌」を意味するギリシャ語「Hebe-erryeke」だろう と書かれています。
ギリシャ神話の「女神ヘーベ」は、「主神ゼウス」と「女神ヘラ」との娘です。
「永久の青春の女神(goddess ofeternal youth)」で、 神々の宴会にお酌をする役割を持っていました。
ギリシャ語「Hebe-erryeke」とは
もともと「Hebe」という言葉は、ギリシャ語で「青春(youth)」 という意味です。
一方でラテン語には「ヘペオ hebeo(鈍感だ)」、「hebes (鈍感の)」、「hebesco (麻痺する)」という言葉があります。
そこから「感覚が鈍くなる」とか、「精神が錯乱する」とか、「へべれけになる」という意味の言葉が、ヨーロッパ各地に多く存在します。
それらの言葉は、「Hebeのお酌」によって「酩酊する」ということからきている、と考えられます。
イタリア語の「ebbro [ヘベレケの、 夢中の〕」や、「ebbrieta(ヘベレケ)」、「ebberezza(ヘベレケ)」 などは、語頭の 「h-」が省略されたものです。
ギリシャ語に、「erryeka(流す、注ぐ、お酌をする)」という言葉があります。
この言葉がなまると、「エレケ」となります。
「女神へーべ」の「エレケ(お酌)」で、「ヘベレケ」になった、というのが木村鷹太郎の説です。
日本語とギリシア語の祖語が同じでなければ考えにくいため、大正の当時から、こじつけという指摘 がありました。
日本で『へべれけに酔う』というが,『へべれけ』とはギリシア語 Hebeerryeke (ヘーベのお酌)の意だろうと木村鷹太郎氏がいわれたが,いかにもそうであろう.『へべのれけ』と,『の』を入れた言い方もあるのが,いっそうそうらしく思わせる.日本の辞書で『へべれ』の語原を説明したのはないらしい.日本語の範囲内だけでは,どんなにこじつけても,説明はつかぬようだが,ギリシア語と対照するとどうやら関連があらしい.『へっついさん』と Hestia (かまどの神)など他にも多くの神話伝説,言語民俗上の類似関連があることなども思いあわすべきである.
引用:『時事英語研究 = The Study of current English』24(4),研究社出版,1969-04. 国立国会図書館デジタルコレクション
「へべれけ」は死語なのか考察してみた
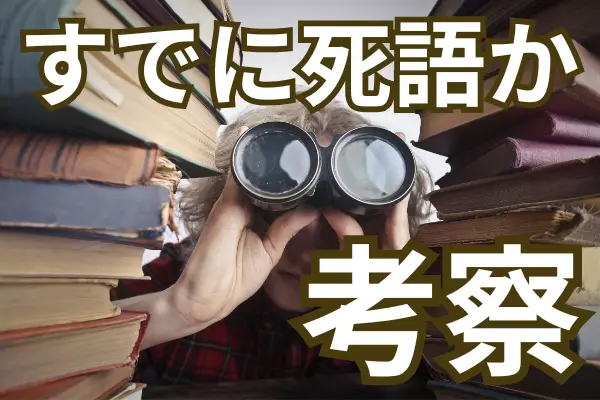
「へべれけ」の死語度は60%です。
最近では「べろべろに酔う」などの表現が主流で、あまり使わない表現になってきています。
しかし少なくとも古くは明治時代からある日本語のため、「まったく意味がつうじない」ということはありません。
「へべれけ」まとめ
本記事では「へべれけ」の意味と、死語になっているかを考察しました。
「へべれけ」の死語度は60%です。
「べろべろに酔う」などの表現のほうが、一般に通じやすくなっています。
人気の記事
タップできる索引