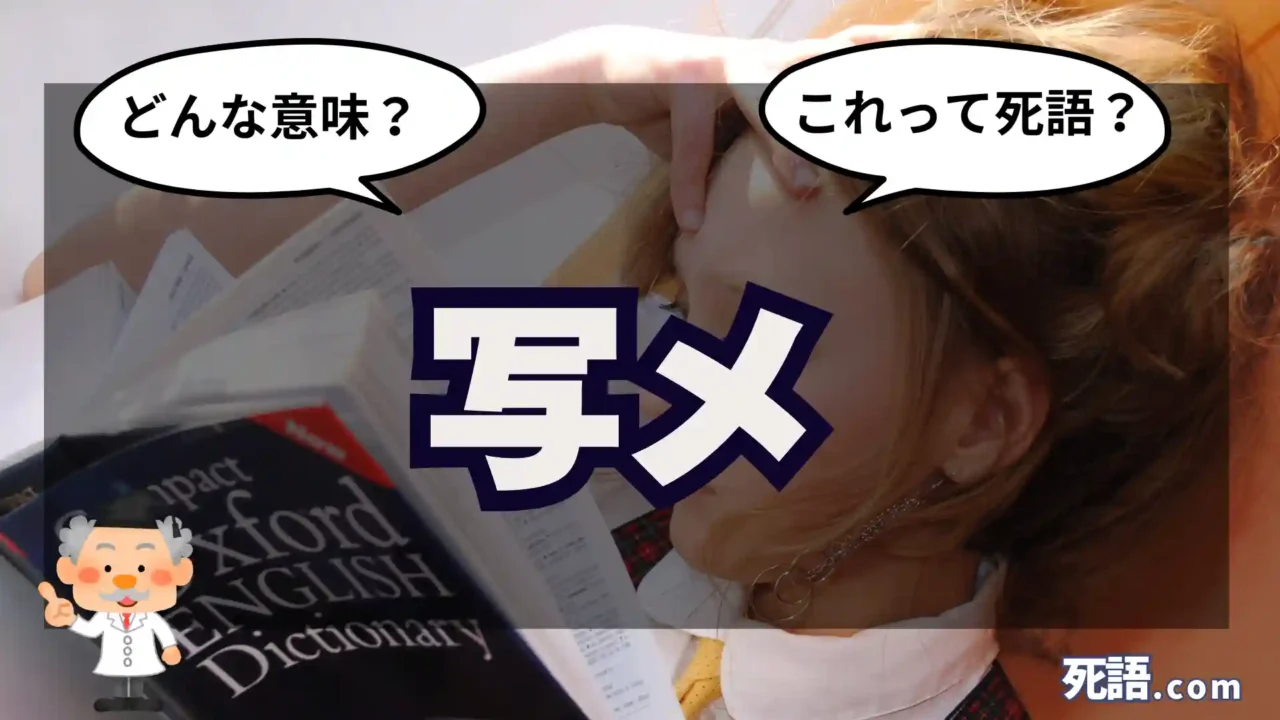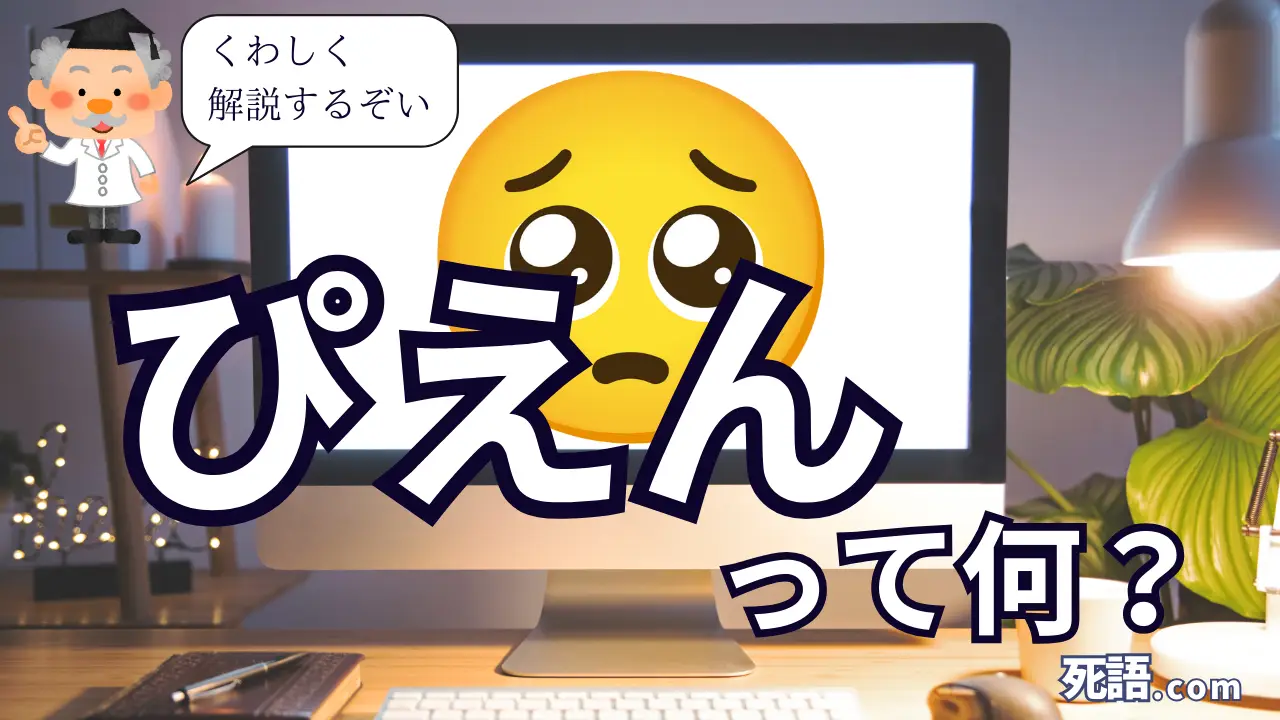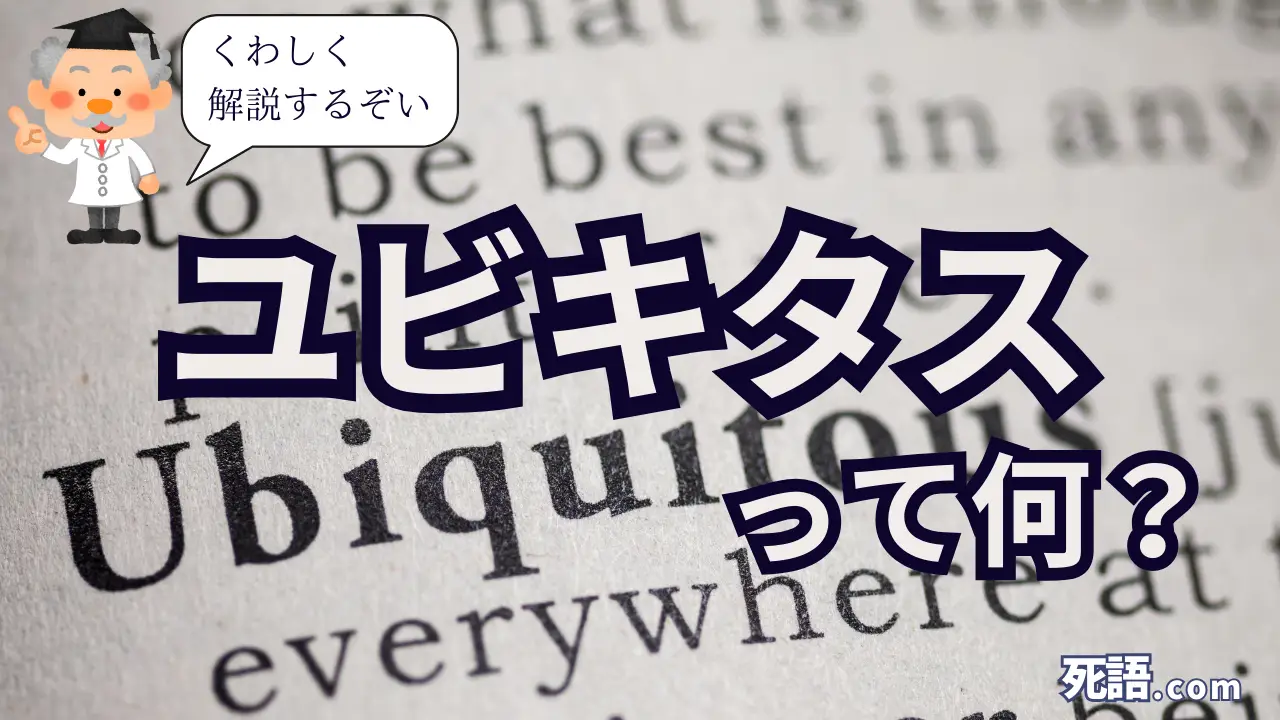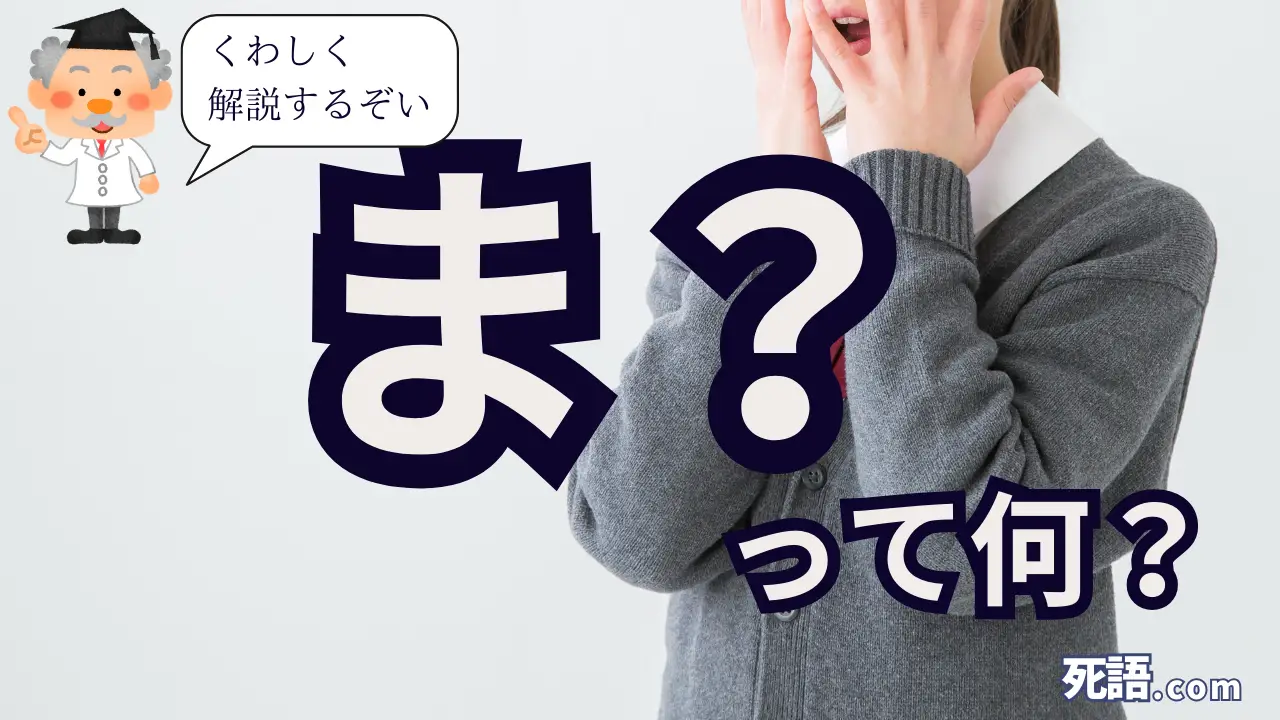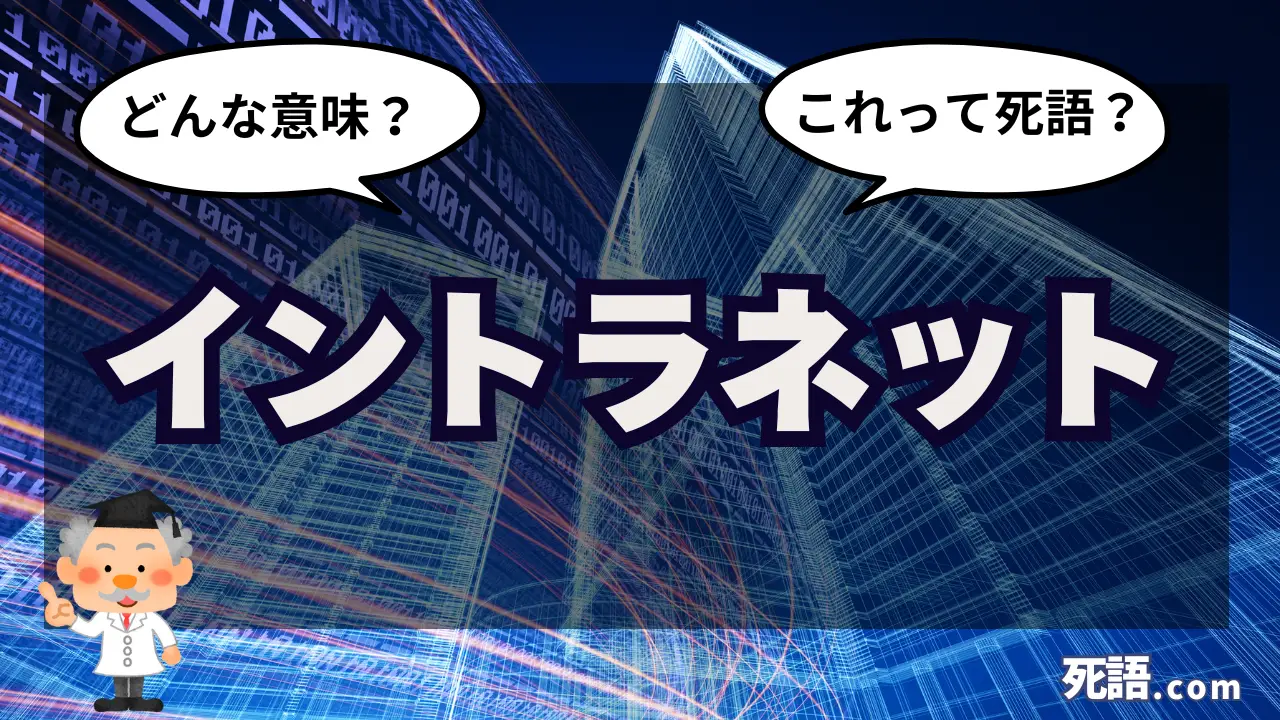「あ、UFO!」は1970年代から1980年代はじめまで使われていた流行語です。
時代の流れで自然と使われなくなり、死語になりました。
使い方としては勝負事の最中に、相手の注意を引き、集中をみだす目的で使われました。
現代社会で使った場合、「古い」、「恥ずかしい」と見られたり、「なつかしい」と感じたり、そもそも意味として通じない可能性があります。
そこで本記事では「あ、UFO!」について、言葉の意味や使い方、時代背景について解説します。
タップできる索引
本記事のリンクには広告が含まれています。
『あ、UFO!』という死語の意味
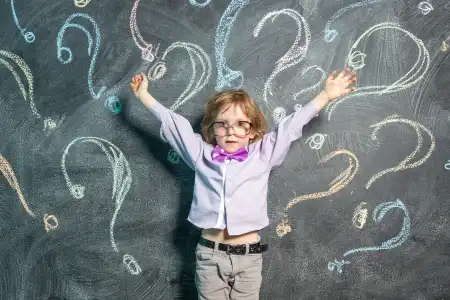
「あ、UFO!」という死語の意味は以下のとおりです。
「あ、UFO!」は相手の注意をそらすために使われた
「あ、UFO!」は、相手と勝負ごとや論争をしているときに、相手の気をそらす目的で使われていました。
相手の興味を引いて、集中がみだれた隙に、自分が有利にことを進める手段です。
UFOは「Unidentified Flying Object」の略で、未確認飛行物体のことです。
一般的には空飛ぶ円盤がイメージされます。

『あ、UFO!』という死語が流行した時代

「あ、UFO!」は1970年代から1980年代はじめに流行した死語です。
1960年代の子供たちの関心ごとに「空飛ぶ円盤」があった
1960年代に刊行されたこども雑誌「少年マガジン」や「少年サンデー」には、「恐竜」や「ゼロ戦などの戦記もの」があつかわれていました。
なかでも特集されることが多かったのが「空飛ぶ円盤」です。
背景には、アポロ計画などに触発された「宇宙へのあこがれ」や、「SF小説」が全盛だったことがあります。
1964年の東京オリンピックまでは、テレビもまだ普及していなかったため、この頃のこども雑誌で育った世代が、次の時代のSF文化や、オカルトブームを支えました。
1970年代から1980年代はじめまで使われていた流行語
1970年代から1980年代はじめには、空前のオカルトブームがあり、世の中全体がUFO(未確認飛行)に大変大きな興味を寄せていました。
不安な世相が背景にあり、『ノストラダムスの大予言』や『日本沈没』などの終末を予感させる作品がベストセラーとなりました。
超能力者、ネッシーなどのUMA(Unidentified Mysterious Animal=未確認生物)などがテレビに頻繁に登場し、UFOも数多く取り上げられました。
ノストラダムスの大予言
『ノストラダムスの大予言』は、1973年に五島勉が書いた、ノストラダムスの予言を解釈した本です。
1999年7月の人類滅亡説を提唱してベストセラーとなり、日本でのオカルトブームの先駆けとなった作品です。
日本沈没
『日本沈没』は、地殻変動により日本列島が海中に沈んでいく過程と、それに直面する日本人の運命を描いた小松左京のSF小説です。
1973年3月20日に光文社から上下2巻で同時刊行され、たちまち大ベストセラーとなりました。
1973年と2006年の2回、映画化されています。
1回目の映画化
公開年: 1973年
監督: 森谷司郎
主演: 藤岡弘
2回目の映画化
公開年: 2006年
監督: 樋口真嗣
主演: 草彅剛
『あ、UFO!』という死語が流行した時代背景

「あ、UFO!」が流行した背景として、オカルトブームからくる、UFOへの世間の強い関心が下敷きになっています。
1970年代は高度経済成長期を経験して、物質的な豊かさを享受していました。
日本社会はその豊かさから、科学技術への懐疑や、未知なるものへの探求心が高まっていました。
1975年2月23日の「甲府事件」などをきっかけに、UFOへと世間の関心が集められるようになっていきました。
「甲府事件」で2人の小学生が宇宙人に接触?
1975年(昭和50年)の2月23日に、山梨県甲府市のぶどう畑に、UFOが着陸したとされる事件です。
2人の小学生が宇宙人らしき搭乗者を目撃して、1人は宇宙人に肩を叩かれたとされています。
また現場のぶどう畑では、コンクリート柱の倒壊や、地面に穴が開いているなどの痕跡が見つかったとされています。
目撃証言や、物的証拠から、社会的に大きな注目を集めました。
当時の小学生は学校の屋上では輪になってUFOを呼んでいた?
当時の一部の小学生は、UFOを呼ぶために学校の屋上で、ぐるぐるまわりながら「ベントラ、ベントラ、スペースピープル」と唱えていました。
「ベントラ、ベントラ、スペースピープル」という呪文は、アメリカのUFOコンタクティーであるジョージ・ヴァン・タッセルが発祥とされます。
コンタクティーとは、宇宙人やUFOと接触したと主張する人のことです。
日本でこの呪文が知られるようになったのは、1957年に設立された「宇宙友好協会」が紹介したことがきっかけとされています。
UFOの存在が、日本社会に深く浸透していたことをあらわす、エピソードのひとつです。
1970年代に親しまれたUFOの映像作品や音楽
1970年代のUFOブームを象徴するものとして、UFOに影響を受けた作品が多く作られました。
アニメ|UFOロボ グレンダイザー
『UFOロボ グレンダイザー』は、永井豪さんが原作のマジンガーシリーズの第3作として制作された、東映動画のロボットアニメです。
1975年(昭和50年)10月5日から1977年(昭和52年)2月27日までフジテレビ系列で毎週日曜日19:00 – 19:30に全74話が放送されました。
宇門大介の名で地球人として暮らす主人公は、実はフリード星の王子デュークフリードで、ベガ星連合軍による地球侵略を、グレンダイザーで阻止する物語です。
グレンダイザーは、スペイザーと呼ばれる円盤と合体すると飛行能力が得られる設定になっています。
平均視聴率は20.9%を記録し、商業的にも成功をおさめました。
2024年には、約50年越しに、リブート版『グレンダイザーU』が放送されています。
アニメ|UFO戦士ダイアポロン
『UFO戦士ダイアポロン』は、1976年にエイケンが制作したロボットアニメです。
TBS系で1976年4月から9月まで全26話が放送されました。
続編の『UFO戦士ダイアポロンII アクションシリーズ』は同年10月から翌年2月まで放送されています。
主人公タケシは地球で育ったアポロン星の王子で、宇宙エネルギー「エナルジーハート」を巡り、あおぞら学園の仲間とともに「UFO少年団」を結成して、ダザーン軍団と戦う物語です。
日本初の「複数ロボットが合体して巨大ロボットになる」設定を導入した、画期的なアニメでした。
40周年を迎えた2016年には、記念プロジェクトが始動しました。
アニメ映画|これがUFOだ!空飛ぶ円盤
『これがUFOだ!空飛ぶ円盤』は、1975年3月21日に公開された東映動画制作のアニメーション映画です。
UFOや宇宙人に関する有名な事件や写真をテーマにした、16分間のドキュメンタリー風アニメーションで、東映まんがまつりで上映されました。
UFOの特徴や、宇宙人の想像図、UFOの正体に迫る内容です。
映画の中では、UFOの目撃事例として有名な「マンテル大尉事件」や「ケネス・アーノルド事件」なども紹介されました。
特撮ヒーロー|UFO大戦争 戦え! レッドタイガー
『UFO大戦争 戦え! レッドタイガー』は、1978年4月から12月まで東京12チャンネル(テレビ東京)で放送された、全39話の特撮テレビ番組です。
日本防衛研究所の天野博士が建造した巨大ロボット要塞・ランボルジャイアントを巡る物語。
ブラックデンジャー魔王に博士を殺された3人の遺児が、謎のヒーロー・レッドタイガーの助けを借りながら、ランボルジャイアントを完全なロボット要塞にするための旅にでます。
1970年代の特撮ヒーロー作品の中でも、SFと特撮を融合させた、独特の世界観を持つ意欲的な作品でした。
宇宙円盤大戦争
『宇宙円盤大戦争』は1975年7月26日に東映まんがまつりで公開された、ロボットを題材にした短編アニメ映画です。
物語は、ヤーバン帝国に故郷を滅ぼされたデュークフリード王子が、超兵器ガッタイガーで宇宙を脱出し、地球にたどり着きます。
宇門大介として平和に暮らしていたところ、ヤーバン軍が全宇宙征服のために、ガッタイガーを追って地球にやってきます。
デュークフリード王子は、地球をまもるため、ガッタイガーに乗り込んでヤーバン軍と戦うことになります。
コミカライズや映像ソフト化もされていて、DVDやBlu-ray BOXに収録されています。
音楽|ピンクレディー「UFO」
『UFO』は、1970年代後半に爆発的な人気を博した女性デュオ「ピンクレディー」の楽曲です。
「ピンクレディー」のメンバーは、根本美鶴代さん(愛称:ミー、現:未唯mie)と、増田啓子さん(愛称:ケイ、現:増田惠子)の2人です。
6枚目のシングルとして、1977年12月5日にリリースされ、販売枚数は195万枚をこえる最大のヒット曲となりました。
オリコンチャートで10週連続1位を記録しています。
1977年に電通主催の「南太平洋・裸足の旅」に参加した、作詞家の阿久悠がイースター島でUFOらしき物体を目撃した経験から、着想を得たとされています。
『あ、UFO!』という死語の使用例
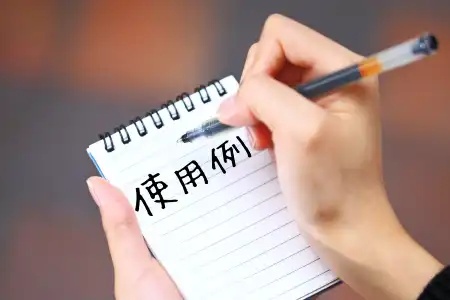
「あ、UFO!」という死語は、たとえば以下のようなときに使用されていました。
「あ、UFO!」の使用例 ① 卓球の試合
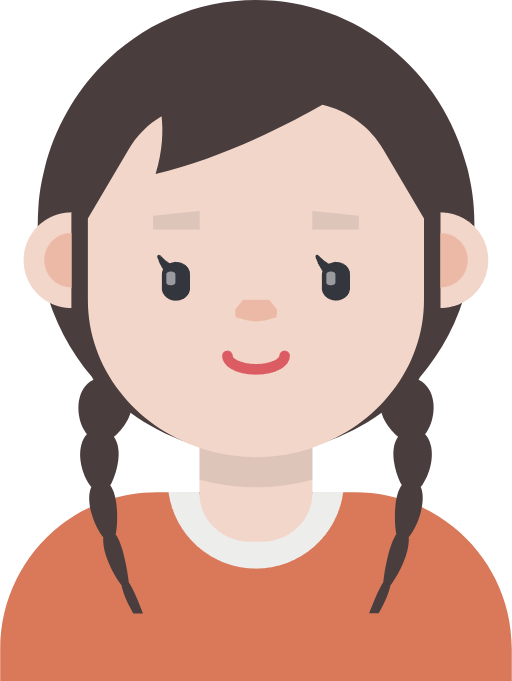 おさげちゃん
おさげちゃんマッチポイント!
次の球を返して決める!



あ、UFO!



目を離した隙に打ち込んでやる!
「あ、UFO!」の使用例 ② 腕相撲
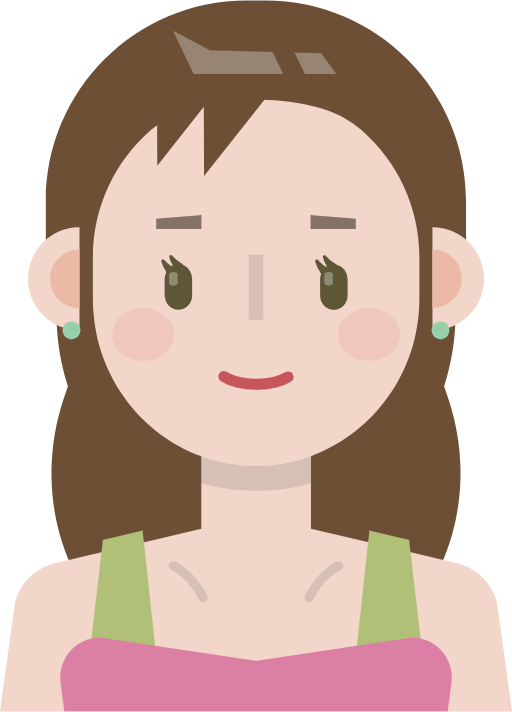
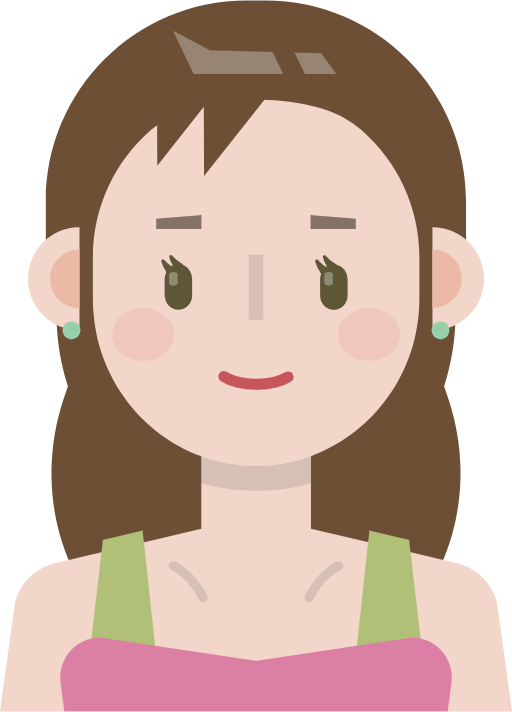
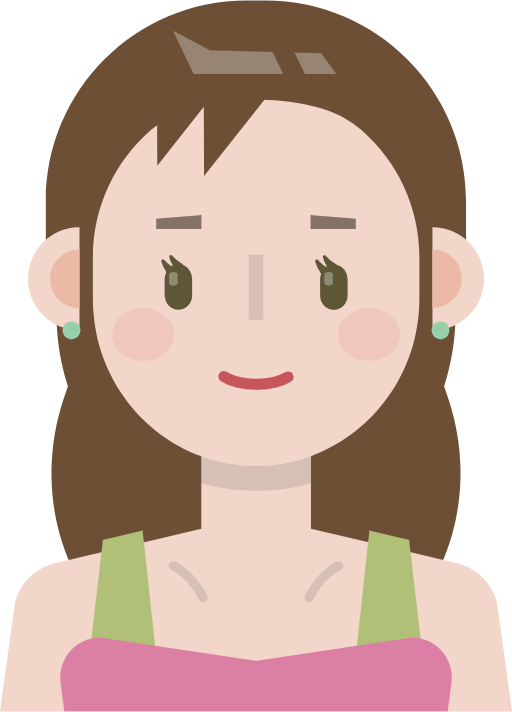
せーの……!



あ、UFO!



力を抜いている隙に倒しちゃえ……!
現代でも『あ、UFO!』が使われていないか調査してみた
現代でも「あ、UFO!」が使われていないか調査してみました。
ネコちゃんに「あ、UFO!」といっている例を発見!
YouTubeの「もちまる日記」さんの動画に、使用例がありました。
当時の「コトを有利に進める目的」での使い方ではありませんが、相手の注意を引く点では同じです。
ネコちゃん、かわいいですね。
『あ、UFO!』まとめ
「あ、UFO!」は1970年代から1980年代はじめに流行した死語です。
当時はオカルトブーム、UFOブームに日本中がわいていました。
「あ、UFO!」が流行したのも、そういったオカルトやUFOに注目する世相が背景にありました。
人気の記事
タップできる索引